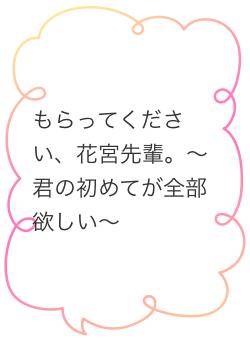学校へ行かなくて当然。そんなこと初めて言われた。
不登校になったら、担任からいつになったら登校できるかと家に電話が掛かってくるようになったし、両親も、理由を頑なに話さない私の様子を伺いつつ、夜な夜などうしたら私が学校へ行けるのか話し合っていた。
入学式に連絡先を交換した程度のクラスメイトから、誰かに頼まれて渋々送ったような、当たり障りのない私を待っているというメッセージもくるようになった。
みんな、学校へ行かない私がおかしいと、行かないと言う選択をした私を肯定してはくれなかった。
洸は私がサンダルを履く間もなく手を引き、海に向かって砂浜を進む。足の裏に、太陽に焼かれ熱くなった砂の感触が伝わる。
やがて波打ち際に辿り着き、洸はデニムが濡れることを気にせず、全く躊躇いなく海へと入っていく。それを見て驚いた私は立ち止まった。