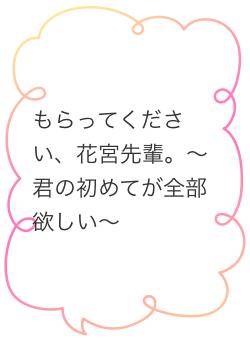情けなく声が震える。
後悔して、私と同じくらい苦しんで欲しかった。側から聞けばきっと馬鹿だと思われる。
だけど、私にとっては、これしか──。
「都こそ、勿体ねーよ」
その言葉に、私は隣に座る洸に視線を向けた。
洸の目は、痛々しいほど歪められていた。
「そんな奴らの為に命を投げ出すなんて、勿体ねぇよ。それにそいつら、都が死んだところで時間が経ったらお前のことを忘れて生活するぞ」
「……忘れる?」
「そうだ、忘れる。だから勿体ない」
あっけらかんと告げられた事実に、私は言葉を失った。
散々苦しみ、最後に自分で自分を殺しても、あいつらに恨みを返せるわけではないの?