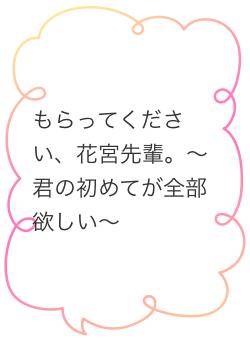祖父母の家から、緩く傾斜したアスファルトの坂道をゆっくりと海に向かい下っていく。
ジリジリと照り付ける日差しが素肌を焼き、汗が滲む。もうすでに帰りたい。
私の隣を歩く洸は、キャップを目深に被り、大きな欠伸をしている。眠いならこんなことしなくていいのに。普通に迷惑だ。
朝食を食べ終え、祖父母に背中を押され家を出されたが、目的地がどこなのかが先ず謎だ。
「あの」
「ん? なに」
「……遊びって、何を」
「夏と言えば?」
「え」
「海だろ」
「は?」
「行くぞー」
坂を下り終え、洸はガードレールに手を掛ける。