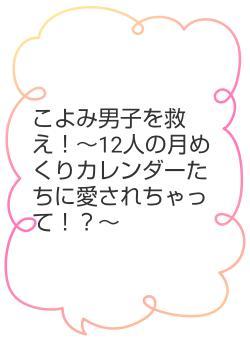聞かなくてもわかる、誰のことを言っているのか。
そんなの1人しかいないもん。
確信に変えたくなかった。
「花絵ちゃんとは小学校から一緒だって、由夢ちゃんも知ってるでしょ?」
「…はい」
椅子に座ったまま、物寂しそうに暁先輩が話す。その声はいつも聞いてるはずなのに、どこか違う人に聞こえた。
「まだ3年生の時だったかな、それまでは花絵ちゃんも笑いかけてくれたんだけど…おはようって何気なく言った時、おはようって返してくれた顔が可愛いなって思ったんだよね」
「………。」
この間が抜ける感じ、すごく暁先輩だ。
あまりに自然にナチュラルにスムーズにノロケるから私の方が戸惑っちゃった。
「だから“笑った顔が可愛いね”って言っちゃったんだよね」
悲しそうに笑った。
眉をハの字にして、少し俯いて。
「それが…よくなかったみたい」
「……。」
「俺は本当に可愛いって思ったからそう言っただけなんだけど、それが逆に傷付けちゃったみたいで」
花絵先輩はわざと暁先輩の前だけ笑わないようにしていた。
それも自分を殺しているように、必死に。
それって何の意味があったんだろう?
「…だから笑ってほしくて、こんなことしてるんだ」
“暁先輩は何で青春リクエスション始めたんですか?”
それは暁先輩の花絵先輩を誰より愛しく想う気持ち。
「何したら笑ってくれるんだろーって考えてみたんだけど、案外早くすることなくなっちゃって。じゃあ誰かに聞いてみようかな?って思い付いたのが“青春リクエスション”だった」
あれもこれも全部、花絵先輩への気持ちでいっぱいだった。
私が想って来たこの時間も、暁先輩の中は花絵先輩しかいなかった。
冷ややかな体育館はとても虚しくて。
「マブはそれも全部知った上で手伝ってくれてるんだ。まぁあいつは楽しけりゃなんでもって感じだろうけど」
暁先輩が鍵盤の蓋を閉じて立ち上がった。
全然楽しくなさそうに私に笑って見せた。
「バカでしょ。好きな子の笑顔見たくてこんなことしてるの」
そんな風に笑わないでください。
私はどんな顔したらいいんですか。
「…軽蔑した?」
「…いいえ、そんなこと…ないです」
好きな子、それだけが頭に残った。
そんなの1人しかいないもん。
確信に変えたくなかった。
「花絵ちゃんとは小学校から一緒だって、由夢ちゃんも知ってるでしょ?」
「…はい」
椅子に座ったまま、物寂しそうに暁先輩が話す。その声はいつも聞いてるはずなのに、どこか違う人に聞こえた。
「まだ3年生の時だったかな、それまでは花絵ちゃんも笑いかけてくれたんだけど…おはようって何気なく言った時、おはようって返してくれた顔が可愛いなって思ったんだよね」
「………。」
この間が抜ける感じ、すごく暁先輩だ。
あまりに自然にナチュラルにスムーズにノロケるから私の方が戸惑っちゃった。
「だから“笑った顔が可愛いね”って言っちゃったんだよね」
悲しそうに笑った。
眉をハの字にして、少し俯いて。
「それが…よくなかったみたい」
「……。」
「俺は本当に可愛いって思ったからそう言っただけなんだけど、それが逆に傷付けちゃったみたいで」
花絵先輩はわざと暁先輩の前だけ笑わないようにしていた。
それも自分を殺しているように、必死に。
それって何の意味があったんだろう?
「…だから笑ってほしくて、こんなことしてるんだ」
“暁先輩は何で青春リクエスション始めたんですか?”
それは暁先輩の花絵先輩を誰より愛しく想う気持ち。
「何したら笑ってくれるんだろーって考えてみたんだけど、案外早くすることなくなっちゃって。じゃあ誰かに聞いてみようかな?って思い付いたのが“青春リクエスション”だった」
あれもこれも全部、花絵先輩への気持ちでいっぱいだった。
私が想って来たこの時間も、暁先輩の中は花絵先輩しかいなかった。
冷ややかな体育館はとても虚しくて。
「マブはそれも全部知った上で手伝ってくれてるんだ。まぁあいつは楽しけりゃなんでもって感じだろうけど」
暁先輩が鍵盤の蓋を閉じて立ち上がった。
全然楽しくなさそうに私に笑って見せた。
「バカでしょ。好きな子の笑顔見たくてこんなことしてるの」
そんな風に笑わないでください。
私はどんな顔したらいいんですか。
「…軽蔑した?」
「…いいえ、そんなこと…ないです」
好きな子、それだけが頭に残った。