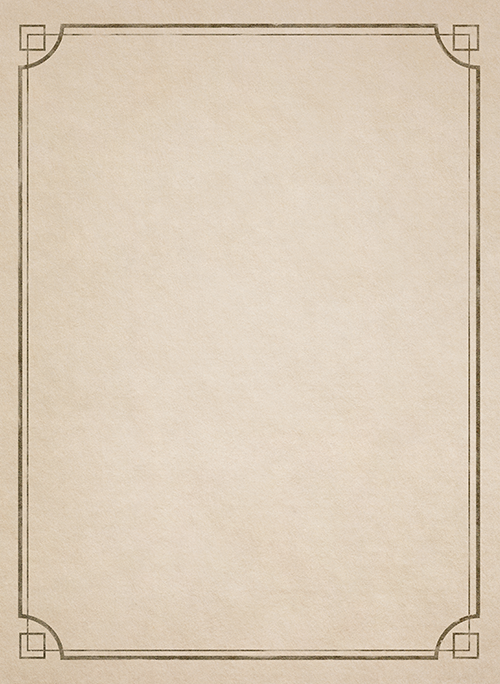「許しなど、はなから期待していない。これは復讐なのですから」
自身に言い聞かせる様な口ぶりで語った女は、言葉とは不釣り合いに歪に笑っていた。
「お前たちが奪った全てを奪い返す。ただそれだけのことなのですから」
呟きの様な語りは、砂利を打ち付ける雨がかき消している。
騒がしい筈なのに、音が消えているかのような静寂を感じた。
「何一つ、何一つなにひとつ、一欠けらも残してやるものか。全て。奪われた全てを奪い返す」
憎悪か。
醜悪なそれは、その言葉がよく似合った。
言葉の割には表情は疲れた様な笑みを絶やさない。
もとから何も残ることはないと知っての嘲笑であった。
無意味な復讐に、飽き飽きとしながらも自身ではもう立ち止まることも出来ない。
そんな女の刃が向けられた先が自分達であった。
「…きさまぁ」
金切り声をあげて立ちあがったのは怒りによる勢いであった。
そこで、膝が折れようなんて思うわけもなかった。
それほどの怒りがあった。
忘れられるほどに。