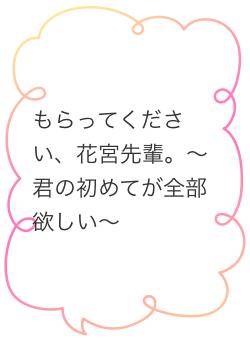「もう、私は一人で生きていくしかないんだ……」
寒さが寂しさを増幅させ、それはやがて諦めへと変わっていく。
誰かと寄り添って生きたくて、自分を変えようとしたら捨てられて。
……もういい、誰にも分かってもらえなくていい。一人でも、私なら大丈夫だ。
「だから、この凍死しそうな状況も……自分でなんとかしなきゃ」
――――ザッ
カバンを持って立ち上がろうとしたその時、すぐ側で砂利を踏みしめるような音がした。
「お姉さん、何してるの?」
突然現れたのは、銀髪で外国人のような見た目の、高い身長にモッズコートを着込んだ、パッと見20代前半くらいの青年だった。
その青年は私を見て目を見開き、男性にしては少し高めで、柔らかな声を発した。
まさか人に会えるとは思わず、驚いて言葉を失う私を見つめ、青年は空を指差す。