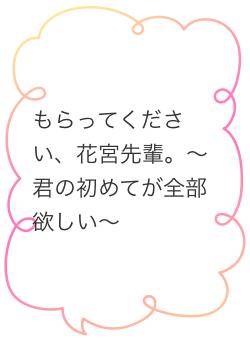「(……ダメ、だ)」
自分の気持ちに気付いてしまった瞬間、指先がピクリと自分の意思通りに動いた。同時に私は唇が触れ合う寸前でユキを思い切り突き飛ばす。
ユキは驚いたように目を見開き、路地の壁に背を預ける。
「……な、にしてるのよ。ユキ」
「……」
「私達は、一線を越えてしまったら一緒にはいられないのよ……?」
許されない。
私がユキと一緒にいられる理由は、私がユキの保護者だから。安心して預けられる『居場所』だから。
振り絞った声は情けないくらいにか細くて、だけどユキに見抜かれてはいけない、そう思うと自然と背筋が伸びた。