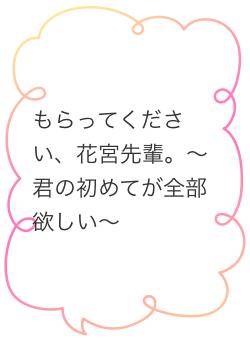私を責めてもいい、罵倒してもいい。無事でよかった、家に帰って来て欲しいって……それが家族じゃないの?
あの子は一人で眠れなくて、毎晩寝床を探してさまよっていたのに、こんなに立派な家があっても家族の心が通っていなかったら意味なんてないでしょう?
考えていることが口から滑り落ちてしまいそうで、ぐっと奥歯を噛み締めユキのお母さんが何を言うのを待つ。
「心配は、もちろんしていました」
「ならっ」
「でも、私がユキを連れ戻すことはできないんです。……私が、あの子を追い込んだから」
雪がはらはらと空から舞い落ちてくる。
このユキのお母さんの目は、ユキの何かを深く考えている時のそれととても似ている。
突然、手袋越しに手を握られ肩が跳ねる。寒くて静かな夜の空気に溶けるように、ユキのお母さんは言葉を繋いだ。
「私は――――」
「なに、してるの」