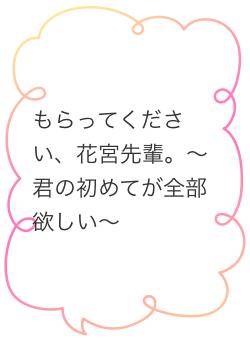「ユキくんが、毎日代わる代わる寝床を探し歩いていたので、保護するような形で家においていました」
「……はい」
「家族のことを頑なに話さなかったものですから、無理には聞かず本人が言いたくなるまで待っていて、こんなにご挨拶が遅くなってしまって申し訳ありません」
「……」
頭を下げ、ユキのお母さんの言葉を待つ。
しかし、私が自分の履くブーツのつま先をいくら眺めていても会話は途切れたままだった。
恐る恐る顔を上げると、ユキのお母さんは何かを堪えているような、複雑な表情を浮かべている。
そして次の瞬間、予想もつかなかった言葉を発した。