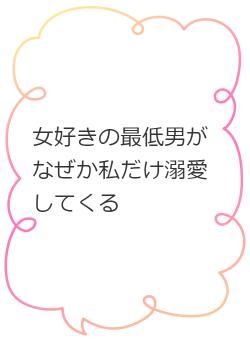私は無視して机の中に教科書をしまい始めた。
「ねぇ、聞いてんの? なんたがいるとクラスの雰囲気悪くなるんだけど」
「だよねぇ。だってあんた友達のこと覚えないもんね」
上地さんが声を立てて笑う。
その言葉にさすがに胸がチクリと刺されるような痛みを感じた。
みんな私の病気を知らないし、私自身も隠しているから仕方のないことだ。
これは私が選んだことなんだから。
そう言い聞かせてみても、なかなか胸の痛みは取れない。
「早く特別学級に帰れよバカなんだから」
秋山くんの大声とゲラゲラ笑う声に、体の奥ジワリと黒い感情が浮かんでくるのを感じた。
なにも知らないくせに、特別学級の子たちはもっともっと勉強が進んでいて、あんたたちなんかよりもよっぽど頭がいい子ばかりだ。
そう言ってやりたい気持ちをどうにか押し殺す。
最初は私だってみんなと同じ偏見を持ち、勘違いをしていた。
そう思うと、秋山くんをせめることはできない。
私はただひたすら、ホームルームが始まるまでの時間を耐えていたのだった。
「ねぇ、聞いてんの? なんたがいるとクラスの雰囲気悪くなるんだけど」
「だよねぇ。だってあんた友達のこと覚えないもんね」
上地さんが声を立てて笑う。
その言葉にさすがに胸がチクリと刺されるような痛みを感じた。
みんな私の病気を知らないし、私自身も隠しているから仕方のないことだ。
これは私が選んだことなんだから。
そう言い聞かせてみても、なかなか胸の痛みは取れない。
「早く特別学級に帰れよバカなんだから」
秋山くんの大声とゲラゲラ笑う声に、体の奥ジワリと黒い感情が浮かんでくるのを感じた。
なにも知らないくせに、特別学級の子たちはもっともっと勉強が進んでいて、あんたたちなんかよりもよっぽど頭がいい子ばかりだ。
そう言ってやりたい気持ちをどうにか押し殺す。
最初は私だってみんなと同じ偏見を持ち、勘違いをしていた。
そう思うと、秋山くんをせめることはできない。
私はただひたすら、ホームルームが始まるまでの時間を耐えていたのだった。