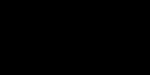「透子、もう食べないのか?」
「……いらない」
「おい、透子……?」
わたしはそのまま寝室に入り扉を締め、ベッドに潜り込んだ。
「藍……」
やっぱり何も言ってくれないんだ、朝のこと……。あんな場面、見なきゃ良かった……。
藍の後なんて、付けなければ良かった……。なんて、後悔ばかりが押し寄せてくる。
「透子、どうした? 大丈夫か?」
寝室のドアをノックした藍は、そうドア越しに問いかけてきた。
「透子、やっぱり体調悪いのか?」
それでも何も言わないわたしに、藍は「入るぞ」と声をかけてから、ドアを開けて寝室に入ってきた。
「透子、どうした?何かあったのか?」
「……うるさい。一人にして」
「透子、何を怒ってるんだ?」
怒ってる? そりゃあ、あんな場面を見せられたら、怒りたくもなるに決まってるでしょ……。
夫である藍とあの女の、キス現場を目撃してしまったのだから。そんなの見せられたら、怒るに決まってる。
「なぁ、透子。どうしたんだよ?」
「別に、なんでもないよ」
藍がわたしを心配しているのか、わたしのそばへとやって来る。
「そんな訳、ないよな? 体調悪いなら、病院行くか?」
「うるさいな……。あっち行ってよ!」