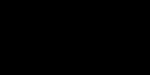「これからはこんな古臭い旅館なんかより、我々が経営するリゾートホテルの時代なんだよ。……少し考えれば分かるだろ。 ね、女将?」
「ちょっと待ってください。ここは古臭くなんてありません!……ここは、ここは歴史ある立派な旅館です!こんなにもたくさんの人に愛されてきたから、夕月園はここまで営業してこれたんです。 それはわたしたちじゃなくて、ここに来てくれるたくさんのお客様がいたおかげです!」
わたしは悔しくて、つい立ちあがってそう言葉を吐き出した。
「……やめなさい、透子」
「でも、女将……!」
だけど女将は、それを止めた。
「ええから、座りなさい」
冷静さを失ったわたしと、冷静さを常に保つ女将では、歴然の差だった。
「……はい」
わたしは言われた通りにするしかなかった。
「女将、決断は早い方がいいですよ?」
「……こんなことして、あなた方になんのメリットがあるというのかしら?」
女将の言うとおりだ。こんなことして、この人たちになんのメリットがあるというのだろうか。
「メリット?そんなものはない。……ただ目障りなだけだよ、ここがね」
そう言って女将に向かって、あの男はニヤリと笑ったのだった。
その笑顔は、まさに【悪魔】だったーーー。