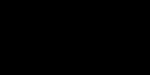わたしの心配をしてくれなんて、わたしは彼に頼んだ覚えはない。
この人が勝手に心配してるだけだ。
「透子、君のお腹の子の父親は俺だ。俺には君たちを守る責任があるんだ。 だから無茶をして透子に何かあったら、困るんだよ」
「なんで?なんでそこまでして……。バカじゃないの?」
困るのよ、そういうの……。余計なお世話だ。
「バカでもいい。俺は君とお腹の子を幸せにしたい。……ただ、それだけだ」
なぜだか分からないけど、そう言われたら何も言い返せなくなってしまった。
「……何なの。わたしにとってあなたは、特別な人でも何でもないのに」
変な人……。わたしにそこまでしてくれる理由が分からない。
「分かってる。……けど俺は、君のことを大事にしたいと思ってる。この先もずっと、大切にしたい」
そう言って彼は、わたしの頬に手を乗せて撫でるように触れてきた。
「……悪いけどわたしは、あなたのことを好きになんてならない」
ずっと憎んでる。今でもずっと……。憎くて仕方ないのに。
「なら、俺のことを好きにさせる。 透子が俺のことを好きになれるように、努力するつもりだ」
「なにそれ……。バカじゃないの」
「ああ、俺はバカだよ」
一言そう言われて、口付けを交わされた。