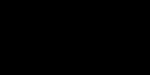それからは本当にあっという間に過ぎていった。相変わらず藍の溺愛は増えていくばかりで、わたしの心はザワザワしている。
わたしのお腹はどんどん大きくなっていって、気が付けば歩くのがやっとな感じだ。
「透子、俺がやるって」
「大丈夫だって」
「ダメだ。ケガしたら大変だろ?」
洗濯物を干しているわたしの横で、藍は心配そうな表情でわたしのことを見ていた。
「本当に大丈夫だって。藍は心配し過ぎなんだよ」
と言ってみても、藍は聞く耳を持たないのだ。
「だって透子はもう妊婦なんだぞ?腹だってこんなに大きくなってるんだし」
藍はその大きくなっているお腹に手を触れながら、そんなことを言ってきた。
「……まぁ、そうだね」
「だろ? 透子が無理して倒れたり、赤ちゃんに何かあってからじゃ遅いだろ?」
そう言われたわたしは「……分かった。じゃあお願いしようかな」と言った。
「素直なのはいいことだ。 お前の身体はお前一人のものじゃないんだ。時には誰かに頼ることも、大事だぞ、透子」
そう言われたら何も言い返せなくなることを、藍はきっとわかっているのだろう。
「……うん。ありがとう」
確かに藍の言う通りだな……。なんでも一人でやろうとしてしまうのが悪いクセだと思う。