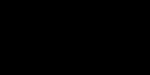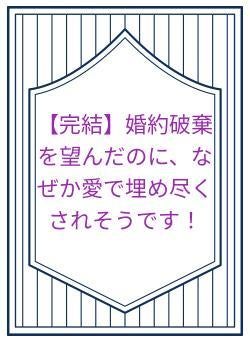爽太さんはそんなわたしを見て、泣きそうになっていた。
「……良かった。本当に、無事で……良かった」
「爽太、さん……。わたし、生きてるんですね……」
「当たり前だろ?……優秀な救命医が、助けてくれたんだから」
優秀な……救命医?それって……。加古川先生のこと?
「……良かった。わたし、生きてて良かったっ……」
そう思うだけで、涙がこぼれた。生きてて良かった。……今本当に、そう思う。
こうしてまた爽太さんの顔を見ることが出来て、爽太の声を聞くことが出来たことは、まさに奇跡とさえ感じた。
「紅音……。頼むからもう、これからはあまり無茶するな。お前に何かあったら、俺もう……不安になるから」
「……はい。ごめんなさい」
「でも本当に、良かった。……また紅音にこうやって触れることが出来て、良かった。安心した」
そう言って紅音さんは、わたしの頬を撫でておでこをコツンとくっつけてきた。
「……爽太さん、心配かけて、ごめんなさい」
「いいんだ。……紅音が生きてさえくれれば、それでいいんだよ」
その言葉に嬉しくて、わたしは爽太さんに抱きついた。