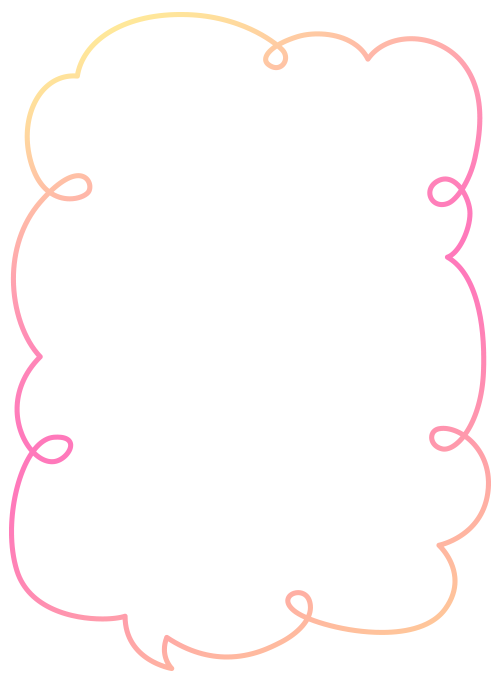今もまだ大粒の雨が窓ガラスを叩き続ける。
時計の針はすでに20時を回っている。
え……20時?
「今日はここに泊っていこう。明日の朝出発するから瑠偉は荷物をまとめておけよ?」
「えっ、あ……うん」
心ここにあらずの状態で小さく頷く。
おかしい……。おばあちゃんがまだ帰ってきていないなんて絶対におかしい。
この時間に帰ってこないことなど一度もなかった。
「センセ、瑠偉トイレに行きたいんだけど。行ってきてもいい?」
「ああ、いいぞ」
「ありがと」
あたしのスマホは先生が預かっている。
警察に通報されないという安心感からか先生はついてこようとはしなかった。
部屋から出て玄関の前を通り過ぎようとしたとき、ふと玄関のたたきに目が行く。
ひゅっと喉の奥が鳴った。
全身に鳥肌が立ち、呼吸が荒くなる。
そこにはおばあちゃんが普段愛用している靴が揃えて置いてあった。
どういうこと……?いつの間にかおばあちゃんはかえってきていたの?
でも、帰ってくるとおばあちゃんは必ず『ただいま』と声をかけるはずだ。
その声が聞こえなかった。雨の音でかき消された?
帰ってきたときそこまで確認していなかったけど最初から置いてあった?
妙な違和感に心臓がドクンドクンッと不快な音を立てて鳴り続ける。
急かされるようにトイレに向かい扉を開けたものの、そこにおばあちゃんの姿はない。
よかった……。
以前もトイレの中で転倒し、あたしが帰ってくるまで床で座り込んでいたことがあった。
ホッと胸を撫で下ろした時、ふとお風呂場に目が行った。
「あれ……?」
脱衣所の引き戸が10センチほど開いている。
不思議思って近付いていくと、ツンっとした異臭が鼻についた。
「なに……?」
排泄物のような刺激臭がお風呂場から漂ってくる。
恐る恐る脱衣所の扉を開けて電気をつけると、浴室のすりガラスの奥に大きな何かがあるのがみてとれた。
匂いはそこから流れ出てきているようだ。
「え」
黒くて大きな何かはピクリともしない。
「なに……?なんなの……?」
すりガラスを勢いよく開けると、浴室の床の上で横たわっていたのは祖母だった。
失禁してしまっているのか、浴室の床は排泄物で汚れていた。
「おばあちゃん!?どうしたの?おばあちゃん!?」
仰向けで倒れていたおばあちゃんは目を開いたまま息絶えていた。
瞳孔は開き、体は冷たくなりわずかに固くなっている。
「なんで!?どうして……!?おばあちゃん!!起きてよおばあちゃん!!」
もう死んでいると分かっていても、体をゆすって名前を呼ぶ。
「きゅ、救急車……!!」
立ち上がろうとしたとき、足の裏が滑り手をつき何とか難を逃れたもののおばあちゃんの排泄物が手のひらにべったりとこびりついた。
「ひっ!!」
顔を歪めていると、騒ぎに気付いた先生がやってきて浴室の中を覗き込んだ。
「センセ!!おばあちゃんが……倒れてて……だから、救急車を――」
「バカな子だな、瑠偉は。呼べるわけがないだろう。そうしたら俺が警察に捕まっちまう」
「え?」
「昼前に家を訪ねたらババアがいたんだ。瑠偉と付き合ってるっていったら帰ってくださいって追い返されそうになってなぁ」
先生の笑顔に震えあがる。
時計の針はすでに20時を回っている。
え……20時?
「今日はここに泊っていこう。明日の朝出発するから瑠偉は荷物をまとめておけよ?」
「えっ、あ……うん」
心ここにあらずの状態で小さく頷く。
おかしい……。おばあちゃんがまだ帰ってきていないなんて絶対におかしい。
この時間に帰ってこないことなど一度もなかった。
「センセ、瑠偉トイレに行きたいんだけど。行ってきてもいい?」
「ああ、いいぞ」
「ありがと」
あたしのスマホは先生が預かっている。
警察に通報されないという安心感からか先生はついてこようとはしなかった。
部屋から出て玄関の前を通り過ぎようとしたとき、ふと玄関のたたきに目が行く。
ひゅっと喉の奥が鳴った。
全身に鳥肌が立ち、呼吸が荒くなる。
そこにはおばあちゃんが普段愛用している靴が揃えて置いてあった。
どういうこと……?いつの間にかおばあちゃんはかえってきていたの?
でも、帰ってくるとおばあちゃんは必ず『ただいま』と声をかけるはずだ。
その声が聞こえなかった。雨の音でかき消された?
帰ってきたときそこまで確認していなかったけど最初から置いてあった?
妙な違和感に心臓がドクンドクンッと不快な音を立てて鳴り続ける。
急かされるようにトイレに向かい扉を開けたものの、そこにおばあちゃんの姿はない。
よかった……。
以前もトイレの中で転倒し、あたしが帰ってくるまで床で座り込んでいたことがあった。
ホッと胸を撫で下ろした時、ふとお風呂場に目が行った。
「あれ……?」
脱衣所の引き戸が10センチほど開いている。
不思議思って近付いていくと、ツンっとした異臭が鼻についた。
「なに……?」
排泄物のような刺激臭がお風呂場から漂ってくる。
恐る恐る脱衣所の扉を開けて電気をつけると、浴室のすりガラスの奥に大きな何かがあるのがみてとれた。
匂いはそこから流れ出てきているようだ。
「え」
黒くて大きな何かはピクリともしない。
「なに……?なんなの……?」
すりガラスを勢いよく開けると、浴室の床の上で横たわっていたのは祖母だった。
失禁してしまっているのか、浴室の床は排泄物で汚れていた。
「おばあちゃん!?どうしたの?おばあちゃん!?」
仰向けで倒れていたおばあちゃんは目を開いたまま息絶えていた。
瞳孔は開き、体は冷たくなりわずかに固くなっている。
「なんで!?どうして……!?おばあちゃん!!起きてよおばあちゃん!!」
もう死んでいると分かっていても、体をゆすって名前を呼ぶ。
「きゅ、救急車……!!」
立ち上がろうとしたとき、足の裏が滑り手をつき何とか難を逃れたもののおばあちゃんの排泄物が手のひらにべったりとこびりついた。
「ひっ!!」
顔を歪めていると、騒ぎに気付いた先生がやってきて浴室の中を覗き込んだ。
「センセ!!おばあちゃんが……倒れてて……だから、救急車を――」
「バカな子だな、瑠偉は。呼べるわけがないだろう。そうしたら俺が警察に捕まっちまう」
「え?」
「昼前に家を訪ねたらババアがいたんだ。瑠偉と付き合ってるっていったら帰ってくださいって追い返されそうになってなぁ」
先生の笑顔に震えあがる。