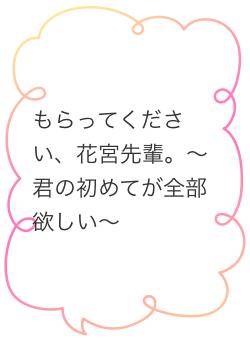きっと俺は、このまま平坦に冷めたまま生きていくんだろう。そう思ってた。
というか、他人に妙に共感したり、分かち合ったり努力したり、それって必要なのか?俺にはよく分からない。しようと思っても、きっとできない。
母さんの腹の中に感情を落としてきたのかもしれない。よく愛理が俺を見てそんなことを言っていた。
────だからあの日。
「だ、大丈夫ですか?」
凛子が電車から飛び出してきたあの日、何故か目が離せない自分に驚いた。
真面目なタイプで、男子から声を掛けられるとオドオドして顔を赤くする。いつも女友達と一緒にいるように、少し内気なタイプの女子。
なのに、助けることを戸惑うくらいの注目を集め、倒れている人間になりふり構わず、なんなら電車を降りてまで駆け寄るあの姿に釘付けになった。
「(すげー、勇気あるじゃん)」
興味が湧いた。自分の想像を軽々と越えた凛子に。
初めて、誰かのことをもっと知りたいと思った。その勇気に触れてみたい、近くにいきたいと思った。
多分、いや絶対に。俺はあの時あの瞬間、凛子にハマっていた。
というか、他人に妙に共感したり、分かち合ったり努力したり、それって必要なのか?俺にはよく分からない。しようと思っても、きっとできない。
母さんの腹の中に感情を落としてきたのかもしれない。よく愛理が俺を見てそんなことを言っていた。
────だからあの日。
「だ、大丈夫ですか?」
凛子が電車から飛び出してきたあの日、何故か目が離せない自分に驚いた。
真面目なタイプで、男子から声を掛けられるとオドオドして顔を赤くする。いつも女友達と一緒にいるように、少し内気なタイプの女子。
なのに、助けることを戸惑うくらいの注目を集め、倒れている人間になりふり構わず、なんなら電車を降りてまで駆け寄るあの姿に釘付けになった。
「(すげー、勇気あるじゃん)」
興味が湧いた。自分の想像を軽々と越えた凛子に。
初めて、誰かのことをもっと知りたいと思った。その勇気に触れてみたい、近くにいきたいと思った。
多分、いや絶対に。俺はあの時あの瞬間、凛子にハマっていた。