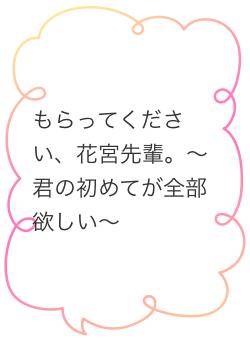「そんなことないよ」
「そんなことあるね。絶対に」
「なんでそんなこと言えるの?」
「目を逸らすから」
「えっ」
「凛子は図星だと目を逸らすから」
陸くんの意志の強い目と視線が合う。この目が苦手だ。昔から、陸くんに嘘がバレなかったことがない。
膝の上でこぶしをぎゅっと握り、私は口を開く。
「何かあった……というより、私の気持ちの問題で」
「気持ちの問題?」
「……今度の花火大会、一緒に行く約束してた人が、仕方のない理由で行けなくなっちゃって」
「…………」
「ほんとに、どうしようもない理由なの……なのに私、自分の気持ちばっかりで」
「…………」
「一緒に、行きたかったって……そっちを優先しないでって……そんなことばっかり思っちゃって」
一回口にしてしまうと、ドロドロと心の内が溢れてくる。嫌な自分が表に出てきてしまう。
なんで仕方ないねって思えないんだろう。自分のことばっかりで、私は────。
「別に自分のことだけじゃなくね?」
あっけらかんとした声に、私は再び顔を上げる。陸くんはさも当然のように、普通に話を続ける。
「行きたかったのに行けなくて残念なんて、当たり前の感情じゃね?どうせ凛子のことだから、本人に文句なんて言わねーだろうし」
「そ、それはもちろん」
「心の中くらい素直じゃなくてどうすんだよ?外も中もいい子ちゃんなんて疲れんだろ?バカ」
「ば、バカってなに?!」
「爆発する前に相談ならいつでも聞く。だから悩むなよ。俺がいつでも笑い飛ばしてやるから」
「っ」
髪の毛をわしわしと撫でられ、何故か泣きそうになった。
今、嫌な感情に呑まれそうになっていた心を陸くんが引き戻してくれた。
嫉妬してもいいのかな?心の中なら平気なのかな?けど、これは紛れもなく彼方くんを好きだという証拠なんだ、否定する必要、ない?
ぎゅっと唇を結び泣くのを我慢すると、陸くんがその顔を見てぶっと吹き出した。