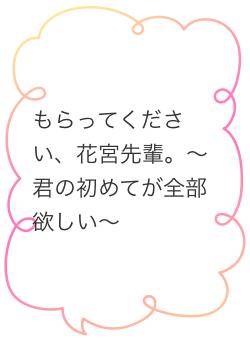「図書室でみんなで勉強してるんです」
「え?奏多が?あの協調性のない?」
「……えっ、はい、一緒に」
「……そっかぁ」
愛理先輩は、廊下の壁に寄りかかり、上を向いた。私はなんとなく気まずくて、早くこの場を立ち去りたくなった。
けど、愛理先輩がぽつりと言葉を溢す。
「奏多にも友達がたくさんできたんだね」
「沢山……ってほどではないですけど、ちゃんといますね」
「私がいないと、ダメだと思ってだんだけど……すっかり成長したんだね」
奏多くんが成長することは良いことなはず。なのに、愛理先輩の声があまりにも寂しそうで苦しそうで、なんて言葉を掛けたら良いのか分からない。
夕日が照らす廊下で、愛理先輩は話を続ける。その姿が本当にきれいで、見惚れてしまいそうになる。
「私達、家が近所で姉弟みたいに育って……本当にいつも一緒だったの」
「そう、なんですね」
「だけど大きくなってからは、奏多、何を考えてるか分からないことが多くなってさ」
愛理先輩が私の目を覗き込む。その視線は静かな嫉妬を含む、突き刺すようなものだった。
「……片山さんは、奏多と付き合ってるの?」
その言葉に、喉がグッと詰まるような感覚に陥り、思わず後退りそうになる。
告白予約をされてるなんて、言えない。
私はなんとか声を振り絞った。
「つ、付き合ってません」
「……そっか」
私の言葉に、愛理先輩は目を見開く。そして、視線を伏せた。
付き合ってはない、けど────。
「けど……奏多くんは、大切な存在です」
「……うん」
────大切で、好きな人だ。
私の答えに、愛理先輩は寄りかかっていた身体を起こした。
そして、わたしに一歩近づく。そして、その形の良い唇がゆっくりと開く。
「私も、奏多が大切だよ」
「は、はい」
「またね、片山さん」
愛理先輩は、私の横をすり抜け廊下の向こうへ歩いて行ってしまった。
けど、今ので分かった。
…………愛理先輩は、奏多くんを弟だなんて思ってない。
「先輩も、奏多くんを好きなんだ」
※※※※