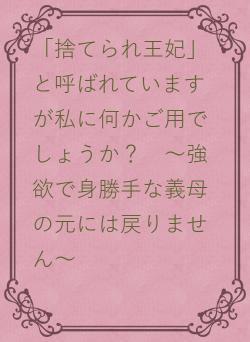その後、アニエスとベルナールは王都の中心近くにあるトレスプーシュ家の城に向かった。
ふだん使わない城であるにもかかわらず、きちんと手入れの行き届いた美しい城だった。フォールの城が要塞を兼ねた剛の城であるならば、こちらは社交のための柔の城といった風情だ。
華美ではないが洗練された調度品や内装で整えられている。
「綺麗なお城ですね」
「年に数回しか使わないがな」
ベルナールは言い、「そのうち暇を見つけて、ソフィやカサンドルと王都に遊びに来た時に、使うといい」と続けた。
明るい居間に落ち着くと、やや真剣な面持ちでベルナールは言った。
「アニエス、おまえの親に冷たいことを言って悪かった」
「冷たくなんかないですよ。閣下に無心なんかして、私が恥ずかしかったです。お父様がどうお考えかは知りませんが、自分のことは自分でやってほしいです」
すっぱりと言い切ったアニエスに、ベルナールが笑う。
優しさとぬるい同情をはき違えない、地に足の着いたアニエスの答えを好ましく思ったようだ。
「実の親とは縁が薄くとも、これからは、俺たちがおまえの家族だ。ソフィはおまえの姉でもあるし、カサンドルもおまえを娘のように思っている。親に甘え損ねた分を取り返すくらい、ぞんぶんに甘えて暮らせばいい」
それまでも不幸だったとは思わないが、フォールに行ってからのアニエスはとても幸せだ。ソフィやカサンドルだけでなく、デボラやメロディ、兵士たちも、みんなすごくよくしてくれる。
にこにこ笑って、アニエスはベルナールにそう告げる。
「閣下もいますし、毎日、すごく楽しいです」
「そうか」
挨拶を済ませたと言えるのかビミョーだが、もともと親の承諾が必要なわけではない。
バシュラール王国の結婚は双方の合意で成り立つ。式を挙げ、証文に神官のサインをもらえば、晴れて二人は正式な夫婦である。
「フォールに帰ったら、式を挙げよう」
黒い瞳にじっと見つめられて、アニエスはドキドキしながら頷いた。
「閣下……」
「そろそろ、閣下ではなく、ベルナールと呼ばないか?」
「ベルナール……、閣下」
ぶっと、ベルナールが噴き出す。
「少しずつ慣れてくれ。できれば敬語もやめよう。兵士たちと話す時のように話してくれると嬉しい」
「はい」
「アニエス……」
長い腕に抱き寄せられて、心臓の鼓動が速まる。
「愛している。俺の妻になってくれるな?」
「か、閣下……」
「ベルナールだ」
なんだか胸がいっぱいになった。
どうやらそういうことになったようだとなんとなく理解し、「俺の子を産んでくれ」がプロポーズの言葉で、きっとベルナールはこういう言葉は言わないのだろうと思っていた。
ふいを突かれて、アニエスは思わず涙ぐんでしまった。
「返事がないぞ」
「は、はい! よろしくお願いします!」
大きな声で答えたら、また少し笑われた。
「バルゲリーが大丈夫だと言うのだから大丈夫だろうが、ムンドバリの攻撃があったのは事実だ。せっかくの王都だが、明日にはフォールに発とうと思う」
「はい」
「フォールに着いて、ムンドバリの一件が片付いたら、すぐに結婚式だ」
「はい」
一週間も経たないうちに、二人は正式に夫婦になる。
なのに、その一週間が待てないと言い、その夜、ベルナールはフライングでアニエスをゲットした。
そのへんが前後することには全体的にゆるい文化がバシュラール王国にはあり、アニエスもベルナールを責めようとは思わなかった。
もともとけしからん男であるベルナールにしては、それでもよく我慢したほうなのだ。
二人きりでフォールまで帰る道中を思えば、とても身が持たないだろう。
潮時である。これで責めるのは酷というものだ。
ふだん使わない城であるにもかかわらず、きちんと手入れの行き届いた美しい城だった。フォールの城が要塞を兼ねた剛の城であるならば、こちらは社交のための柔の城といった風情だ。
華美ではないが洗練された調度品や内装で整えられている。
「綺麗なお城ですね」
「年に数回しか使わないがな」
ベルナールは言い、「そのうち暇を見つけて、ソフィやカサンドルと王都に遊びに来た時に、使うといい」と続けた。
明るい居間に落ち着くと、やや真剣な面持ちでベルナールは言った。
「アニエス、おまえの親に冷たいことを言って悪かった」
「冷たくなんかないですよ。閣下に無心なんかして、私が恥ずかしかったです。お父様がどうお考えかは知りませんが、自分のことは自分でやってほしいです」
すっぱりと言い切ったアニエスに、ベルナールが笑う。
優しさとぬるい同情をはき違えない、地に足の着いたアニエスの答えを好ましく思ったようだ。
「実の親とは縁が薄くとも、これからは、俺たちがおまえの家族だ。ソフィはおまえの姉でもあるし、カサンドルもおまえを娘のように思っている。親に甘え損ねた分を取り返すくらい、ぞんぶんに甘えて暮らせばいい」
それまでも不幸だったとは思わないが、フォールに行ってからのアニエスはとても幸せだ。ソフィやカサンドルだけでなく、デボラやメロディ、兵士たちも、みんなすごくよくしてくれる。
にこにこ笑って、アニエスはベルナールにそう告げる。
「閣下もいますし、毎日、すごく楽しいです」
「そうか」
挨拶を済ませたと言えるのかビミョーだが、もともと親の承諾が必要なわけではない。
バシュラール王国の結婚は双方の合意で成り立つ。式を挙げ、証文に神官のサインをもらえば、晴れて二人は正式な夫婦である。
「フォールに帰ったら、式を挙げよう」
黒い瞳にじっと見つめられて、アニエスはドキドキしながら頷いた。
「閣下……」
「そろそろ、閣下ではなく、ベルナールと呼ばないか?」
「ベルナール……、閣下」
ぶっと、ベルナールが噴き出す。
「少しずつ慣れてくれ。できれば敬語もやめよう。兵士たちと話す時のように話してくれると嬉しい」
「はい」
「アニエス……」
長い腕に抱き寄せられて、心臓の鼓動が速まる。
「愛している。俺の妻になってくれるな?」
「か、閣下……」
「ベルナールだ」
なんだか胸がいっぱいになった。
どうやらそういうことになったようだとなんとなく理解し、「俺の子を産んでくれ」がプロポーズの言葉で、きっとベルナールはこういう言葉は言わないのだろうと思っていた。
ふいを突かれて、アニエスは思わず涙ぐんでしまった。
「返事がないぞ」
「は、はい! よろしくお願いします!」
大きな声で答えたら、また少し笑われた。
「バルゲリーが大丈夫だと言うのだから大丈夫だろうが、ムンドバリの攻撃があったのは事実だ。せっかくの王都だが、明日にはフォールに発とうと思う」
「はい」
「フォールに着いて、ムンドバリの一件が片付いたら、すぐに結婚式だ」
「はい」
一週間も経たないうちに、二人は正式に夫婦になる。
なのに、その一週間が待てないと言い、その夜、ベルナールはフライングでアニエスをゲットした。
そのへんが前後することには全体的にゆるい文化がバシュラール王国にはあり、アニエスもベルナールを責めようとは思わなかった。
もともとけしからん男であるベルナールにしては、それでもよく我慢したほうなのだ。
二人きりでフォールまで帰る道中を思えば、とても身が持たないだろう。
潮時である。これで責めるのは酷というものだ。