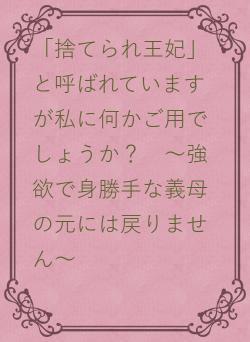それからベルナールは小さくまとめた旅の荷物の中から、革の袋を二つ取り出しテーブルの上に置いた。
紐を解くと、中から金貨が現れる。かなりの枚数だ。
父が目を輝かせて、革袋に手を伸ばした。
ベルナールは、サッと革袋を引いて、父の手から遠ざけた。
「これが何だか、わからないだろうな」
口調がいつものベルナールに戻っている。
「あんたたちの話を聞いて、俺は、アニエスがフォールに来た理由がわかった。フォールに来てくれたことには感謝するが、あんたたちがアニエスにしたことには、ちょっとした憤りを覚える」
「わ、我々が、アニエスにしたこと?」
「むしろ、しなかったことか」
親としての愛情を十分に与えなかった。そうベルナールは言った。
「幼い頃に修行に出して、ずっと会っていなかったのは知っている。急に帰ってきて戸惑ったのもわかる。だが、ここはアニエスにとって、唯一の家だろう。なぜ、帰ってすぐに旅に出なければならないんだ」
「あ、アニエスは、自分から……」
「あんたらが、安心してここにいていいと言わなかったからじゃないのか。仮にもアニエスの生みの親だから、あまりひどいことを言うつもりはないが、あんたらは自分のことしか考えてない。少しもアニエスを大事にしていない。さっきからのやり取りで、俺にはそれがよくわかった」
王太子を平気で蹴る男である。アニエスの親ということで、これでも最大限のオブラートに包んでしゃべっている。
そうでなければ、「クソ野郎」の一言で全てだったはずだ。
「これは、アニエスが稼いだ金の一部だ。わずかな金しか持たずに家を出され、聖女として施術をしながら旅を続け、フォールに着いてからもたくさんの患者を癒してきた。初めは銅貨一枚、ニッケル貨数枚で施術を始め、今ではこの袋にいっぱいの金貨を十二も貯めてある」
「そんなに……?」
呟いたのは、アニエスだ。
衣食住が安定したため金のことはすっかり忘れていたが、聖女として採用された際に、何か契約を交わしたのは覚えている。施術で得た収入の何割がアニエスの取り分になるとか、そんな内容だった。
「なんで金貨を持ってきたんですか?」
「王都には安全な銀行がある」
フォールに置いておいても貯まる一方で使い切れないだろうから、アニエスがそれでよければ、一部をそこに預けておけばいいと思ったのだとベルナールは言った。
たぶん、厳密にはこの金貨はまだベルナールのものなのだ。預ける時にアニエスの名義にするということだろう。
「せっかくだから、王都で何か好きなものを買ってもいいしな。もっとも、欲しいものがあったら、俺がなんでも買ってやるが」
二人の会話を聞いていた両親が、物欲しそうな目でアニエスを伺い見たが、ベルナールがピシャリと言った。
「自分で稼げ。援助はしない」
紐を解くと、中から金貨が現れる。かなりの枚数だ。
父が目を輝かせて、革袋に手を伸ばした。
ベルナールは、サッと革袋を引いて、父の手から遠ざけた。
「これが何だか、わからないだろうな」
口調がいつものベルナールに戻っている。
「あんたたちの話を聞いて、俺は、アニエスがフォールに来た理由がわかった。フォールに来てくれたことには感謝するが、あんたたちがアニエスにしたことには、ちょっとした憤りを覚える」
「わ、我々が、アニエスにしたこと?」
「むしろ、しなかったことか」
親としての愛情を十分に与えなかった。そうベルナールは言った。
「幼い頃に修行に出して、ずっと会っていなかったのは知っている。急に帰ってきて戸惑ったのもわかる。だが、ここはアニエスにとって、唯一の家だろう。なぜ、帰ってすぐに旅に出なければならないんだ」
「あ、アニエスは、自分から……」
「あんたらが、安心してここにいていいと言わなかったからじゃないのか。仮にもアニエスの生みの親だから、あまりひどいことを言うつもりはないが、あんたらは自分のことしか考えてない。少しもアニエスを大事にしていない。さっきからのやり取りで、俺にはそれがよくわかった」
王太子を平気で蹴る男である。アニエスの親ということで、これでも最大限のオブラートに包んでしゃべっている。
そうでなければ、「クソ野郎」の一言で全てだったはずだ。
「これは、アニエスが稼いだ金の一部だ。わずかな金しか持たずに家を出され、聖女として施術をしながら旅を続け、フォールに着いてからもたくさんの患者を癒してきた。初めは銅貨一枚、ニッケル貨数枚で施術を始め、今ではこの袋にいっぱいの金貨を十二も貯めてある」
「そんなに……?」
呟いたのは、アニエスだ。
衣食住が安定したため金のことはすっかり忘れていたが、聖女として採用された際に、何か契約を交わしたのは覚えている。施術で得た収入の何割がアニエスの取り分になるとか、そんな内容だった。
「なんで金貨を持ってきたんですか?」
「王都には安全な銀行がある」
フォールに置いておいても貯まる一方で使い切れないだろうから、アニエスがそれでよければ、一部をそこに預けておけばいいと思ったのだとベルナールは言った。
たぶん、厳密にはこの金貨はまだベルナールのものなのだ。預ける時にアニエスの名義にするということだろう。
「せっかくだから、王都で何か好きなものを買ってもいいしな。もっとも、欲しいものがあったら、俺がなんでも買ってやるが」
二人の会話を聞いていた両親が、物欲しそうな目でアニエスを伺い見たが、ベルナールがピシャリと言った。
「自分で稼げ。援助はしない」