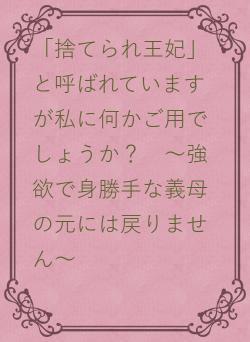フォールの城門でベレニスとドゥニーズに手を振って別れた。
にこにこ笑うアニエスにつられて、兵士たちもなんとなく手を振る。
馬車が見えなくなると、残ったカサンドルに呪いのキモについて、もう少し詳しい話を聞くことにした。
「一応、呪いについては王宮でも限られた人しか知らないことになっていますが、フォールで文献を調べた私の経験では、こちらではむしろご存じの方も多かったように見受けられました」
国防上の秘密という性質上、極秘扱いで辺境軍に共有されていた時期もあったようだとカサンドルは言った。
「ですから、ここではあまり神経質にならずに、お話させていただこうと思います」
本館の居間にはベルナールとアニエスのほかには誰もいなかったが、ドアの外には兵士が立っていた。先ほど聖女の会合に同席した兵六名と合わせて、秘密の保持に関してはベルナールが全責任を負うことを請け合った。
「呪いはバシュラール王国の誕生とともに存在しました」
カサンドルが話し始める。
王国を統べる権限を王に与えたのは魔女だ。呪いはその魔女がかけたものだった。
玉座を与えられながら呪われたのは、王が魔女を裏切ったからだとカサンドルは言った。
「現在、王室に伝わっているのは、呪われたために王が病弱であるということと、それを助けるためには癒しの聖女を后として迎える必要があるという二点です。しかし、聖女が登場するのは建国後数十年が経ってからです。今のところ、正確な文献は見つかっていませんが、おそらく最初の五十年ほどは、王は聖女を得ないまま、命を繋いでいたと考えられます」
そう考える理由として、聖女の養成機関ができたのが322年前であることがあげられる。
これは記録として残っているので、確かだとカサンドルは言った。
「322年前に、次の王のための聖女を養成し始めたのです。つまり、その少し前に、王の病を癒す聖女が現れたのではないかと考えられます。先ほども申し上げた通り、これは偶然だったのだと、私は考えています。たまたま聖女としての力を持つ王妃が現れ、それによって王が聖女に頼るようになったのではないかと」
つまり、カサンドルは、王は元々、聖女の力に頼っていたわけではないと考えた。
「その偶然が起こる前まで、聖女が行う修行は、王自身に課せられたものだったのではないかと、私は考えました」
「王自身に……?」
ベルナールは思わずといったふうに声を漏らした。
「ええ。おそらく……」
頷いて、カサンドルは続ける。
「泉の神様は女神です。私は、あの女神こそ、呪いをかけた魔女だったのではないかと考えています」
にこにこ笑うアニエスにつられて、兵士たちもなんとなく手を振る。
馬車が見えなくなると、残ったカサンドルに呪いのキモについて、もう少し詳しい話を聞くことにした。
「一応、呪いについては王宮でも限られた人しか知らないことになっていますが、フォールで文献を調べた私の経験では、こちらではむしろご存じの方も多かったように見受けられました」
国防上の秘密という性質上、極秘扱いで辺境軍に共有されていた時期もあったようだとカサンドルは言った。
「ですから、ここではあまり神経質にならずに、お話させていただこうと思います」
本館の居間にはベルナールとアニエスのほかには誰もいなかったが、ドアの外には兵士が立っていた。先ほど聖女の会合に同席した兵六名と合わせて、秘密の保持に関してはベルナールが全責任を負うことを請け合った。
「呪いはバシュラール王国の誕生とともに存在しました」
カサンドルが話し始める。
王国を統べる権限を王に与えたのは魔女だ。呪いはその魔女がかけたものだった。
玉座を与えられながら呪われたのは、王が魔女を裏切ったからだとカサンドルは言った。
「現在、王室に伝わっているのは、呪われたために王が病弱であるということと、それを助けるためには癒しの聖女を后として迎える必要があるという二点です。しかし、聖女が登場するのは建国後数十年が経ってからです。今のところ、正確な文献は見つかっていませんが、おそらく最初の五十年ほどは、王は聖女を得ないまま、命を繋いでいたと考えられます」
そう考える理由として、聖女の養成機関ができたのが322年前であることがあげられる。
これは記録として残っているので、確かだとカサンドルは言った。
「322年前に、次の王のための聖女を養成し始めたのです。つまり、その少し前に、王の病を癒す聖女が現れたのではないかと考えられます。先ほども申し上げた通り、これは偶然だったのだと、私は考えています。たまたま聖女としての力を持つ王妃が現れ、それによって王が聖女に頼るようになったのではないかと」
つまり、カサンドルは、王は元々、聖女の力に頼っていたわけではないと考えた。
「その偶然が起こる前まで、聖女が行う修行は、王自身に課せられたものだったのではないかと、私は考えました」
「王自身に……?」
ベルナールは思わずといったふうに声を漏らした。
「ええ。おそらく……」
頷いて、カサンドルは続ける。
「泉の神様は女神です。私は、あの女神こそ、呪いをかけた魔女だったのではないかと考えています」