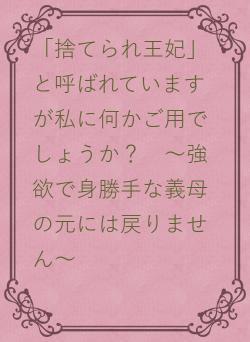ベレニス王太后と二人の聖女は、厳しい監視のもと、城の本館に通された。
アニエスを取り返そうとし、それができないとわかると命を狙ってきたエドモンの所業は、王室と辺境伯軍との間に深い溝を生んでいた。
アニエスを自分のそばに置けば、王家の不安を煽るということをベルナールは理解していた。
王都を攻め落とす気も、玉座を奪う気も、ベルナールにはなかったが、裏を返せば、ベルナールの気分一つで王家はいつでも危機に立たされるということだ。
それを回避するために、再びアニエスの命を狙うことも十分あり得る。
逆に、そんな緊迫した状況の中、王家の者がフォールに近づけば殺される危険もある。
その危険を冒してもアニエスに会わねばならないとやってきた王太后を、追い返すべきではないと考えた。
ただし、たとえベレニス王太后の言葉を信じても、アニエスに危険がないと信じるわけにはいかない。
呪いの秘密について話したいのだと、小声で耳打ちされたが、ベルナールは聖女だけを部屋に通すことに対して、首を縦に振らなかった。
聖女一人に二人の兵士を見張りに付け、アニエスの近くには、いつでも守れるように自分が立つ。
ベレニスは諦めのため息を吐いた。
ものものしい雰囲気の中、四人の聖女の会合は始まった。
「アニエス、久しぶり」
「ベレニス様、ご無沙汰しております」
「元気そうですね」
「はい。ベレニス様もお変わりなく」
兵士に囲まれているものものしさなど一ミリも感じさせず、鋼鉄の心を持つ者同士がなごやかに挨拶を交わした。
「時に、アニエス。あなたは泉の神様の言葉を聞いたことがありますね」
「はい」
「ドゥニーズとカサンドルも」
聖女たちが頷き合い、どんな言葉を聞いたかという話を始めた。
千段の石段を毎日登る者だけに、泉の神様はごくたまに、何かいいことを言ってくれる。
聖女は優しくなければいけないよ、とか。
人を助けるには、自分が強くなくてはいけないよ、とか。
肉は身体にいいよ、とか。
野菜もたべなさい、とか。
綺麗な服を着ていても、心が貧しくてはいけないよ、とか。
どの聖女も、だいたい似たような言葉を聞いていた。
「声は、頭の中に聞こえてくるけど、あれは女神様だと思ったね」
ドゥニーズの言葉に、ほかの三人が頷く。カサンドルが言った。
「ずっと、気になっていることがあって、私はそれについて研究してきました」
バシュラール王国の建国とともに呪いはあった。
なのに、聖女の養成が始まったのは、建国から八十年近く経った後のことだ。
その間に何が起きたのかを、研究しているのだとカサンドルは言う。
「呪いの秘密は決して口外してはならないとされていますが、それは呪い自体に影響するからではありません。口外したら呪いが強まるとか、そういうことはないのです。国防上の戦略として、秘密にされてきただけです」
国防の要とも言える辺境伯軍の兵士に、さりげなく口止めをしながら、カサンドルは続ける。
アニエスを取り返そうとし、それができないとわかると命を狙ってきたエドモンの所業は、王室と辺境伯軍との間に深い溝を生んでいた。
アニエスを自分のそばに置けば、王家の不安を煽るということをベルナールは理解していた。
王都を攻め落とす気も、玉座を奪う気も、ベルナールにはなかったが、裏を返せば、ベルナールの気分一つで王家はいつでも危機に立たされるということだ。
それを回避するために、再びアニエスの命を狙うことも十分あり得る。
逆に、そんな緊迫した状況の中、王家の者がフォールに近づけば殺される危険もある。
その危険を冒してもアニエスに会わねばならないとやってきた王太后を、追い返すべきではないと考えた。
ただし、たとえベレニス王太后の言葉を信じても、アニエスに危険がないと信じるわけにはいかない。
呪いの秘密について話したいのだと、小声で耳打ちされたが、ベルナールは聖女だけを部屋に通すことに対して、首を縦に振らなかった。
聖女一人に二人の兵士を見張りに付け、アニエスの近くには、いつでも守れるように自分が立つ。
ベレニスは諦めのため息を吐いた。
ものものしい雰囲気の中、四人の聖女の会合は始まった。
「アニエス、久しぶり」
「ベレニス様、ご無沙汰しております」
「元気そうですね」
「はい。ベレニス様もお変わりなく」
兵士に囲まれているものものしさなど一ミリも感じさせず、鋼鉄の心を持つ者同士がなごやかに挨拶を交わした。
「時に、アニエス。あなたは泉の神様の言葉を聞いたことがありますね」
「はい」
「ドゥニーズとカサンドルも」
聖女たちが頷き合い、どんな言葉を聞いたかという話を始めた。
千段の石段を毎日登る者だけに、泉の神様はごくたまに、何かいいことを言ってくれる。
聖女は優しくなければいけないよ、とか。
人を助けるには、自分が強くなくてはいけないよ、とか。
肉は身体にいいよ、とか。
野菜もたべなさい、とか。
綺麗な服を着ていても、心が貧しくてはいけないよ、とか。
どの聖女も、だいたい似たような言葉を聞いていた。
「声は、頭の中に聞こえてくるけど、あれは女神様だと思ったね」
ドゥニーズの言葉に、ほかの三人が頷く。カサンドルが言った。
「ずっと、気になっていることがあって、私はそれについて研究してきました」
バシュラール王国の建国とともに呪いはあった。
なのに、聖女の養成が始まったのは、建国から八十年近く経った後のことだ。
その間に何が起きたのかを、研究しているのだとカサンドルは言う。
「呪いの秘密は決して口外してはならないとされていますが、それは呪い自体に影響するからではありません。口外したら呪いが強まるとか、そういうことはないのです。国防上の戦略として、秘密にされてきただけです」
国防の要とも言える辺境伯軍の兵士に、さりげなく口止めをしながら、カサンドルは続ける。