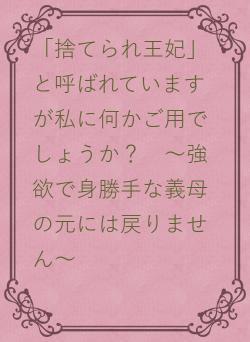アニエスを見送った時、ソフィは、これで全部うまくいくと信じていた。
心を乱すことは聖女としてマイナスになるかもしれないが、アニエスほどの力があれば問題はないだろうとも思った。
実際、アニエスは仕事の上では何も問題なさそうだった。
ただ、アニエスという聖女は、癒しの力以外はどこまでもポンコツだった……。
「あ、閣下……」
診療所の看護師デボラかメロディが小さく呟いただけで、アニエスは飛び上がってどこかへ逃げてしまう。
ベルナールが診療所を覗くと、アニエスは常に留守という状態が続いた。
「やはり、俺はアニエスに嫌われているのか……」
「そんなことはありません! 閣下、いつもの自信はどこへ……」
デボラとメロディが必死に取りなすが、ベルナールは気の毒なほど肩を落として去っていくのだった。
演習場の花壇の前にしゃがみこみ、背中を丸めるベルナールを、兵士たちは代わる代わる励ました。
「嬢ちゃんは、閣下のことが大好きだと言ってましたよ」
「閣下と食べた肉やスープや芋の話を楽しそうにしていました」
すっかり拗ねたベルナールは「どうせ、犬や猫や馬が好きなのと同じ種類の『好き』なんだろう」だの「それは食べ物の話がしたかっただけだろう」などと言って暗い目をしている。
イマイチ強く否定できないところが、兵士たちには辛いところだった。
おそらくベルナールの言う通りだと、誰もが薄々感じていた。
そんなある日、正門前の街道をものものしい馬車の列が走ってきた。
きらびやかな装飾をほどこした中央の馬車には王室の紋章を付けた旗がはためいている。
「王都から、誰か高位の王族がおいでのようです」
「何?」
ベルナールが正門に迎えに出ると、先ぶれが「王太子エドモン殿下のご到着である」と告げた。
「何の用だ」
「王族に向かって無礼な。まずここを通さないか!」
「悪いが、ここは城である前に要塞なんでな。用向きのわからん者を入れるわけにゃあ、いかねえんだよ」
ふだん、アニエスや患者たちを平気で通している兵士たちが、堅牢な盾になって城門を守る。
「もう一度聞く。何の用だ」
キンキラの馬車から、顔だけは整った王太子エドモンが下りてくる。
上品そうな兵士に「殿下」と制止されるが、よろよろとベルナールの近くまで進んできた。
「アニエスを迎えに来た」
ベルナールの目が眇められる。
「アニエスを、返してくれ」
「うるせえ……」
貴様、と護衛の兵士が気色ばむが、辺境軍の兵士に一斉に睨まれて後ろに下がった。
「エドモン様……!」
同じキンキラの馬車からかなりの美人が下りてきた。
「あれが例の金髪碧眼ボンキュッボンか……」
つい、おおお、とざわめく辺境軍の兵士たち。
だが、ベルナールは鼻で笑う。
「たいしたことねえな。アニエスのほうが千倍可愛いじゃねえか」
(閣下……!)
辺境軍の兵士たちは顎が外れるほど口を開いてベルナールを見た。
拳を握りしめたドミニクが、心と心で仲間に伝える。
(人は恋をすると、そういう目になるのだ。閣下は正常だ。みんな落ち着け……)
心を乱すことは聖女としてマイナスになるかもしれないが、アニエスほどの力があれば問題はないだろうとも思った。
実際、アニエスは仕事の上では何も問題なさそうだった。
ただ、アニエスという聖女は、癒しの力以外はどこまでもポンコツだった……。
「あ、閣下……」
診療所の看護師デボラかメロディが小さく呟いただけで、アニエスは飛び上がってどこかへ逃げてしまう。
ベルナールが診療所を覗くと、アニエスは常に留守という状態が続いた。
「やはり、俺はアニエスに嫌われているのか……」
「そんなことはありません! 閣下、いつもの自信はどこへ……」
デボラとメロディが必死に取りなすが、ベルナールは気の毒なほど肩を落として去っていくのだった。
演習場の花壇の前にしゃがみこみ、背中を丸めるベルナールを、兵士たちは代わる代わる励ました。
「嬢ちゃんは、閣下のことが大好きだと言ってましたよ」
「閣下と食べた肉やスープや芋の話を楽しそうにしていました」
すっかり拗ねたベルナールは「どうせ、犬や猫や馬が好きなのと同じ種類の『好き』なんだろう」だの「それは食べ物の話がしたかっただけだろう」などと言って暗い目をしている。
イマイチ強く否定できないところが、兵士たちには辛いところだった。
おそらくベルナールの言う通りだと、誰もが薄々感じていた。
そんなある日、正門前の街道をものものしい馬車の列が走ってきた。
きらびやかな装飾をほどこした中央の馬車には王室の紋章を付けた旗がはためいている。
「王都から、誰か高位の王族がおいでのようです」
「何?」
ベルナールが正門に迎えに出ると、先ぶれが「王太子エドモン殿下のご到着である」と告げた。
「何の用だ」
「王族に向かって無礼な。まずここを通さないか!」
「悪いが、ここは城である前に要塞なんでな。用向きのわからん者を入れるわけにゃあ、いかねえんだよ」
ふだん、アニエスや患者たちを平気で通している兵士たちが、堅牢な盾になって城門を守る。
「もう一度聞く。何の用だ」
キンキラの馬車から、顔だけは整った王太子エドモンが下りてくる。
上品そうな兵士に「殿下」と制止されるが、よろよろとベルナールの近くまで進んできた。
「アニエスを迎えに来た」
ベルナールの目が眇められる。
「アニエスを、返してくれ」
「うるせえ……」
貴様、と護衛の兵士が気色ばむが、辺境軍の兵士に一斉に睨まれて後ろに下がった。
「エドモン様……!」
同じキンキラの馬車からかなりの美人が下りてきた。
「あれが例の金髪碧眼ボンキュッボンか……」
つい、おおお、とざわめく辺境軍の兵士たち。
だが、ベルナールは鼻で笑う。
「たいしたことねえな。アニエスのほうが千倍可愛いじゃねえか」
(閣下……!)
辺境軍の兵士たちは顎が外れるほど口を開いてベルナールを見た。
拳を握りしめたドミニクが、心と心で仲間に伝える。
(人は恋をすると、そういう目になるのだ。閣下は正常だ。みんな落ち着け……)