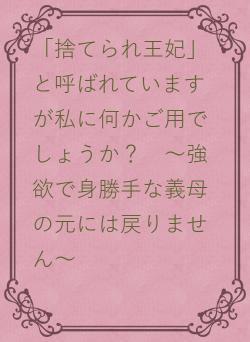旅の汚れや汗臭さは、自分でも気にしていた。
それを誰かに指摘されても、アニエスなら「ごめんなさい」と笑えたのではないか。
かたまり肉にガブリと噛みつくのと同様に、自分にとって必要なこと、その時その時にできることをした上で笑われるなら、それはそれで構わないと、納得して笑顔で生きてきたのではないか。
自分の心に気づいてしまったら、この子はただの女の子になってしまうだろうかと、かすかな躊躇が胸をよぎる。
強くて優しい最高の聖女。
(それでも、アニエスは、ただの女の子になっていいんだわ……)
「アニエス、あなたが泣いてしまったのは、ベルナールに言われたからではないの?」
「閣下に、ですか?」
「例えば、ポールやドミニクに言われたのなら、どうだったか想像してみて」
兵士たちから、音痴だねぇと言われて笑っていたアニエス。
嬢ちゃん、案外可愛かったんだなと言われているのも聞いた。褒めているのだが、よくよく考えると若干ビミョーな言い回しだ。
驚いたようにソフィを見つめ返す小柄な少女に、春の目覚めを促す言葉を口にする。
「ベルナールを、男性として意識していたから、汚れていることや匂いがあることを、恥ずかしく感じたのではないの?」
「か、かかか……? 閣下を? だだだだ……?」
「ええ。あなたは閣下を、男の人だと意識したことはない? 一緒に馬に乗って、背中から抱かれて、ドキドキしなかった?」
「うま……」
アニエスの顔が、カーッとわかりやすく火照っていった。
今、まさにドキドキしていると教えるように両手を胸に押し当てる。
ソフィはにっこり笑って畳みかける。
「その上で、ベルナールのことをどう思う? 好き?」
真っ赤になったアニエスは、今度は口をぱくぱくさせるだけで、はっきりと答えることができなかった。
答えは明確だ。
(世話の焼けること。どっちもどっちで、こうなんだから、ほんとに、もう……)
二言三言、挨拶を交わしてアニエスが退出する。
いつになくよろよろとぎこちない動きを見て、ソフィは満足の笑みを浮かべた。
それを誰かに指摘されても、アニエスなら「ごめんなさい」と笑えたのではないか。
かたまり肉にガブリと噛みつくのと同様に、自分にとって必要なこと、その時その時にできることをした上で笑われるなら、それはそれで構わないと、納得して笑顔で生きてきたのではないか。
自分の心に気づいてしまったら、この子はただの女の子になってしまうだろうかと、かすかな躊躇が胸をよぎる。
強くて優しい最高の聖女。
(それでも、アニエスは、ただの女の子になっていいんだわ……)
「アニエス、あなたが泣いてしまったのは、ベルナールに言われたからではないの?」
「閣下に、ですか?」
「例えば、ポールやドミニクに言われたのなら、どうだったか想像してみて」
兵士たちから、音痴だねぇと言われて笑っていたアニエス。
嬢ちゃん、案外可愛かったんだなと言われているのも聞いた。褒めているのだが、よくよく考えると若干ビミョーな言い回しだ。
驚いたようにソフィを見つめ返す小柄な少女に、春の目覚めを促す言葉を口にする。
「ベルナールを、男性として意識していたから、汚れていることや匂いがあることを、恥ずかしく感じたのではないの?」
「か、かかか……? 閣下を? だだだだ……?」
「ええ。あなたは閣下を、男の人だと意識したことはない? 一緒に馬に乗って、背中から抱かれて、ドキドキしなかった?」
「うま……」
アニエスの顔が、カーッとわかりやすく火照っていった。
今、まさにドキドキしていると教えるように両手を胸に押し当てる。
ソフィはにっこり笑って畳みかける。
「その上で、ベルナールのことをどう思う? 好き?」
真っ赤になったアニエスは、今度は口をぱくぱくさせるだけで、はっきりと答えることができなかった。
答えは明確だ。
(世話の焼けること。どっちもどっちで、こうなんだから、ほんとに、もう……)
二言三言、挨拶を交わしてアニエスが退出する。
いつになくよろよろとぎこちない動きを見て、ソフィは満足の笑みを浮かべた。