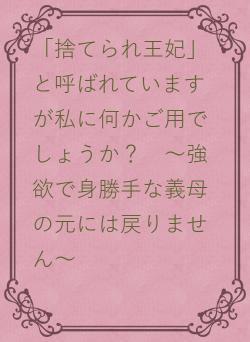さんざん世の女性たちを翻弄し、数々の浮名を流してきた元伝説の色男ベルナールがソフィの私室を去ると、入れ替わるように最高の聖女アニエスがドアをノックした。
「ソフィさん、ただいまです」
「おかえり。旅はいかがでしたか、アニエス」
とても楽しかったです、とアニエスは顔いっぱいを笑顔にして答えた。
「閣下は馬を操るのが上手ですね」
「閣下からもらったお弁当が美味しかったです」
「閣下と一緒に宿で食べたお肉とスープとお芋が……」
「閣下が廊下の寝椅子で……」
「閣下は、私の話を……」
「閣下が……」
茶色の大きな目をキラキラさせて話し続けるアニエスに、ソフィは微笑む。
「アニエス、さっきから、閣下ばかりですねぇ。そんなにベルナールといるのは、楽しかった?」
「はい。閣下とご一緒できてよかったです」
「アニエスは、ベルナールが好き?」
「はい。とても好きです」
屈託のない返事に、ソフィは苦笑してしまった。
おそらくアニエスは、自分自身でもまだ気づいていないのだ。
「アニエス、最初にここに来た時に、あなたは泣いてしまったでしょう?」
「あー……。あの時は、気が緩んでしまって……」
確かにそれもあるだろう。
ベルナールも言っていたように、アニエスにとって王宮を出されてからフォール城に着くまでの日々は、決して楽なものではなかったはずだ。
十八になったばかりの少女が、たった一人で、少ない退職金だけを手に、どこへ行くともなしに旅をする。
自分の技術だけをよりどころに、常に明日の心配をしながら生きていくということが、楽であるはずがない。
アニエスはどんな気持ちであののぼりを作り、背負ってきたのだろうと思うと、ソフィは鼻の奥がじんと痺れて泣きそうになる。
国を追われ、着の身着のままフォールに逃げてきた日のことをソフィは思い出していた。
ソフィには夫がくれた宝石があった。
フォールに着けば両親やベルナールが待っていると信じられた。
それでも、旅は辛く苦しいものだった。
アニエスにはそれすらなかったのだ。
自分にできることを一生懸命にやって、やっと安心できる場所にたどりついて、そこでふいに言われた言葉に傷ついて泣いてしまったというのは、わかる。
けれど、やはりソフィには、理由はそれだけではないように思えてならない。
どんな状況にあっても明るく元気に笑えるアニエスの心は、とても強くてしなやかだ。
簡単には折れない。
「ソフィさん、ただいまです」
「おかえり。旅はいかがでしたか、アニエス」
とても楽しかったです、とアニエスは顔いっぱいを笑顔にして答えた。
「閣下は馬を操るのが上手ですね」
「閣下からもらったお弁当が美味しかったです」
「閣下と一緒に宿で食べたお肉とスープとお芋が……」
「閣下が廊下の寝椅子で……」
「閣下は、私の話を……」
「閣下が……」
茶色の大きな目をキラキラさせて話し続けるアニエスに、ソフィは微笑む。
「アニエス、さっきから、閣下ばかりですねぇ。そんなにベルナールといるのは、楽しかった?」
「はい。閣下とご一緒できてよかったです」
「アニエスは、ベルナールが好き?」
「はい。とても好きです」
屈託のない返事に、ソフィは苦笑してしまった。
おそらくアニエスは、自分自身でもまだ気づいていないのだ。
「アニエス、最初にここに来た時に、あなたは泣いてしまったでしょう?」
「あー……。あの時は、気が緩んでしまって……」
確かにそれもあるだろう。
ベルナールも言っていたように、アニエスにとって王宮を出されてからフォール城に着くまでの日々は、決して楽なものではなかったはずだ。
十八になったばかりの少女が、たった一人で、少ない退職金だけを手に、どこへ行くともなしに旅をする。
自分の技術だけをよりどころに、常に明日の心配をしながら生きていくということが、楽であるはずがない。
アニエスはどんな気持ちであののぼりを作り、背負ってきたのだろうと思うと、ソフィは鼻の奥がじんと痺れて泣きそうになる。
国を追われ、着の身着のままフォールに逃げてきた日のことをソフィは思い出していた。
ソフィには夫がくれた宝石があった。
フォールに着けば両親やベルナールが待っていると信じられた。
それでも、旅は辛く苦しいものだった。
アニエスにはそれすらなかったのだ。
自分にできることを一生懸命にやって、やっと安心できる場所にたどりついて、そこでふいに言われた言葉に傷ついて泣いてしまったというのは、わかる。
けれど、やはりソフィには、理由はそれだけではないように思えてならない。
どんな状況にあっても明るく元気に笑えるアニエスの心は、とても強くてしなやかだ。
簡単には折れない。