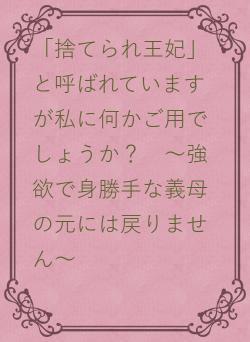城の本館にあるソフィの私室は、開け放たれた窓から流れ込む夏の香りで満ちていた。
「百合かしらね」
「そのようですね。少し切って参りましょうか」
「いいわ。香りだけで十分」
侍女に向かって優しく微笑むソフィは、ベルナールのたった一人の姉だ。他国に嫁いで、嫁いだ先で国を失うという苦しい過去を持つが、そんな日々など忘れたかのような静かな佇まいをしている。
「アニエスとベルナールが戻ったようね」
風に乗って兵士たちの声が聞こえてきた。
アニエスを大層気に入った彼らは、あの手この手でベルナールとアニエスをくっつけようとしている。
凄腕の聖女にずっと城にいてほしいという気持ちもなくはないのだろうが、それ以上に、アニエスという少女のことが、彼らはとても好きなのだ。
それは、ソフィも同じだった。
兵士たちの若干暴走気味な作戦行動を、ソフィもついつい微笑ましい気持ちで見ていた。
「姉上」
まだ外のざわめきが聞こえるうちに、私室のドアが軽く叩かれた。
「ベルナール、珍しいわね」
視察から帰ると、いの一番に記録の整理をする弟が、執務室に行くより前に訪ねてきたことに軽く驚く。
「アニエスがここに来る前に、相談したいことが……」
「いいわよ。何?」
ソフィの向かい側にあるカウチに腰を下ろしながら、しかしベルナールは言葉に詰まっている。
「視察先で、何か問題でもあったの?」
「そういうわけでは……」
「アニエスとは、どうだった?」
突然、ベルナールの顔が廃人のように表情を失った。魂がどこかに行ってしまっている。
「ベルナール?」
はっと我に返ったベルナールが口を開く。
「アニエスは、俺をどう思っているのだろう……」
「どうって……?」
「嫌われてはいないようだが……」
「そうね。あんな失礼のことを言ったのに、奇跡だわ。アニエスが優しい子でよかったわね」
少し顔を歪めたが、ベルナールは静かに頷いた。
「アニエスは、優しい」
そうつぶやいた後で、突然、堰を切ったように、アニエスの魅力について語り始めた。
唇をきゅっと結んで、大真面目な顔で一生懸命施術をする様子が、頼もしいと同時にとても可愛い。
大柄な兵士たちもビックリするような肉への執着と、その食べっぷりに感動する。
歌が下手で、おしゃれも苦手で、けれどいつでもにこにこ笑っているところが素敵だ。
欲がなさ過ぎて寂しい部分もあるが、必要以上に欲張らない姿勢には大いに学ぶものがあった。
「百合かしらね」
「そのようですね。少し切って参りましょうか」
「いいわ。香りだけで十分」
侍女に向かって優しく微笑むソフィは、ベルナールのたった一人の姉だ。他国に嫁いで、嫁いだ先で国を失うという苦しい過去を持つが、そんな日々など忘れたかのような静かな佇まいをしている。
「アニエスとベルナールが戻ったようね」
風に乗って兵士たちの声が聞こえてきた。
アニエスを大層気に入った彼らは、あの手この手でベルナールとアニエスをくっつけようとしている。
凄腕の聖女にずっと城にいてほしいという気持ちもなくはないのだろうが、それ以上に、アニエスという少女のことが、彼らはとても好きなのだ。
それは、ソフィも同じだった。
兵士たちの若干暴走気味な作戦行動を、ソフィもついつい微笑ましい気持ちで見ていた。
「姉上」
まだ外のざわめきが聞こえるうちに、私室のドアが軽く叩かれた。
「ベルナール、珍しいわね」
視察から帰ると、いの一番に記録の整理をする弟が、執務室に行くより前に訪ねてきたことに軽く驚く。
「アニエスがここに来る前に、相談したいことが……」
「いいわよ。何?」
ソフィの向かい側にあるカウチに腰を下ろしながら、しかしベルナールは言葉に詰まっている。
「視察先で、何か問題でもあったの?」
「そういうわけでは……」
「アニエスとは、どうだった?」
突然、ベルナールの顔が廃人のように表情を失った。魂がどこかに行ってしまっている。
「ベルナール?」
はっと我に返ったベルナールが口を開く。
「アニエスは、俺をどう思っているのだろう……」
「どうって……?」
「嫌われてはいないようだが……」
「そうね。あんな失礼のことを言ったのに、奇跡だわ。アニエスが優しい子でよかったわね」
少し顔を歪めたが、ベルナールは静かに頷いた。
「アニエスは、優しい」
そうつぶやいた後で、突然、堰を切ったように、アニエスの魅力について語り始めた。
唇をきゅっと結んで、大真面目な顔で一生懸命施術をする様子が、頼もしいと同時にとても可愛い。
大柄な兵士たちもビックリするような肉への執着と、その食べっぷりに感動する。
歌が下手で、おしゃれも苦手で、けれどいつでもにこにこ笑っているところが素敵だ。
欲がなさ過ぎて寂しい部分もあるが、必要以上に欲張らない姿勢には大いに学ぶものがあった。