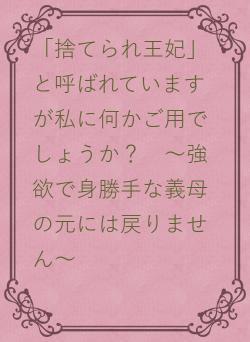城には馬車も何台かあったが、フォールは坂が多く道も悪い。
移動するには馬に乗るほうがはるかに楽だと言われて、アニエスはベルナールの馬に背中から抱かれる感じで乗せてもらった。
のぼりは邪魔になるので、ベルナールが背負った。
「じゃあ、行ってくる」
キリっと告げたベルナールに、兵士たちはにこにこしながら手を振る。
「ごゆっくり~」
「お留守はお任せくださ~い」
『心の病、身体の病、切り傷、擦り傷、やけど、吐き気、腹痛、水虫、なんでも治します』
色の褪せてきたのぼりをはためかせながら、二人はぱかぱかと城下を進んだ。
「アニエス……。いつかはすまなかった」
「いつか? いつかって、いつですか?」
「おまえを泣かせた時のことだ……」
ああ、とアニエスは笑った。
「臭くて汚かったのは本当ですから」
「怒ってないのか」
「怒ってませんよぉ。私こそ、急に泣いたりしてすみませんでした。あの時はほっとしてしまって、つい……」
ふだんのアニエスなら、あんなに簡単に泣いたりしなかったはずだ。
泣いてしまった後で、アニエスはあれこれ考えた。そして、あれは安心したせいだったのだと自分を納得させた。
「ほっとしていたのか」
「はい。やっと、落ち着き先が決まったので、ちょっと気が緩んでしまいました」
旅を続けていて一番堪えたのは、居場所のない心細さだった。
どこへ行くともなく進んでいた頃の、孤独や当てのなさを思うと、今は本当に幸せだと感じる。
「お城に着いて、雇ってもらえてよかったです」
「だが、おまえは……、そんなふうに思っていながら、最初に採用を告げた時は旅を続けるか迷っていると言ったぞ」
厳しい境遇に再び身を置くつもりだったのかと、ベルナールが聞く。
「だって……。できることがあるのがわかっているのに、それをやらないでいるのは、なんだか嫌じゃないですか? 私は聖女ですから、できるだけたくさんの人を治してあげたいんです」
ちょっとカッコよすぎたかなと思って、照れて「うふふ」と笑う。
ベルナールが馬を止めた。
「閣下?」
急に背後から抱きしめられて、アニエスの心臓がドキッと大きく跳ねた。
「……閣下、苦しいです」
「おまえは、強いな。強くて、優しい」
「せ、聖女ですから……」
ドキドキしながら答えた。
――聖女は優しくなければいけないよ。
泉の神様は言っていた。
――人を助けるには、自分が強くなくてはいけないよ。
修行は厳しかったけれど、アニエスは聖女の養成所でたくさんのことを学んだ。
王を癒して国の役に立つことはできなくなったけれど、違う形で自分の力を人のために生かせている。これは、すごく嬉しいことだ。
「聖女になれて、私は幸せです」
「おまえの良さがわからぬ王太子はバカだ」
「不敬罪で罰せられますよ?」
「罰せられるものなら罰してみろ。王の軍が俺を捕らえにきたところで、我がフォール辺境軍を前にして、何ができる」
確かに勝負にならないだろう。
アニエスはまた、ふふふと笑った。ベルナールがぼそりと言った。
「アニエス、俺は決めたぞ」
移動するには馬に乗るほうがはるかに楽だと言われて、アニエスはベルナールの馬に背中から抱かれる感じで乗せてもらった。
のぼりは邪魔になるので、ベルナールが背負った。
「じゃあ、行ってくる」
キリっと告げたベルナールに、兵士たちはにこにこしながら手を振る。
「ごゆっくり~」
「お留守はお任せくださ~い」
『心の病、身体の病、切り傷、擦り傷、やけど、吐き気、腹痛、水虫、なんでも治します』
色の褪せてきたのぼりをはためかせながら、二人はぱかぱかと城下を進んだ。
「アニエス……。いつかはすまなかった」
「いつか? いつかって、いつですか?」
「おまえを泣かせた時のことだ……」
ああ、とアニエスは笑った。
「臭くて汚かったのは本当ですから」
「怒ってないのか」
「怒ってませんよぉ。私こそ、急に泣いたりしてすみませんでした。あの時はほっとしてしまって、つい……」
ふだんのアニエスなら、あんなに簡単に泣いたりしなかったはずだ。
泣いてしまった後で、アニエスはあれこれ考えた。そして、あれは安心したせいだったのだと自分を納得させた。
「ほっとしていたのか」
「はい。やっと、落ち着き先が決まったので、ちょっと気が緩んでしまいました」
旅を続けていて一番堪えたのは、居場所のない心細さだった。
どこへ行くともなく進んでいた頃の、孤独や当てのなさを思うと、今は本当に幸せだと感じる。
「お城に着いて、雇ってもらえてよかったです」
「だが、おまえは……、そんなふうに思っていながら、最初に採用を告げた時は旅を続けるか迷っていると言ったぞ」
厳しい境遇に再び身を置くつもりだったのかと、ベルナールが聞く。
「だって……。できることがあるのがわかっているのに、それをやらないでいるのは、なんだか嫌じゃないですか? 私は聖女ですから、できるだけたくさんの人を治してあげたいんです」
ちょっとカッコよすぎたかなと思って、照れて「うふふ」と笑う。
ベルナールが馬を止めた。
「閣下?」
急に背後から抱きしめられて、アニエスの心臓がドキッと大きく跳ねた。
「……閣下、苦しいです」
「おまえは、強いな。強くて、優しい」
「せ、聖女ですから……」
ドキドキしながら答えた。
――聖女は優しくなければいけないよ。
泉の神様は言っていた。
――人を助けるには、自分が強くなくてはいけないよ。
修行は厳しかったけれど、アニエスは聖女の養成所でたくさんのことを学んだ。
王を癒して国の役に立つことはできなくなったけれど、違う形で自分の力を人のために生かせている。これは、すごく嬉しいことだ。
「聖女になれて、私は幸せです」
「おまえの良さがわからぬ王太子はバカだ」
「不敬罪で罰せられますよ?」
「罰せられるものなら罰してみろ。王の軍が俺を捕らえにきたところで、我がフォール辺境軍を前にして、何ができる」
確かに勝負にならないだろう。
アニエスはまた、ふふふと笑った。ベルナールがぼそりと言った。
「アニエス、俺は決めたぞ」