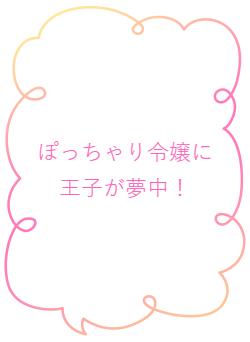あれこれ世話を焼いてくれるお爺さんも、いつか私から離れていくだろう。
それか死ぬ。
皺くちゃな可愛い手に、私のあげた薬草の袋を下げている。
「……」
「寂しそうな顔して。また仲直りできなかったのかい?」
「しないわ」
お爺さんを通り越して扉を開ける。
私はハッとして振り向いた。
「お茶とパイをごちそうさま、お爺さん。気をつけて帰ってね」
「ああ、また明日」
そう、お爺さんとは、こうでなくちゃ。
笑顔で手を振りあって、矍鑠とした背中を見送る。木こりのお爺さんは歳をとっても俊敏で、足腰がしっかりしていて、私が心配するような事は寿命しかない。
部屋に戻って、さっきまでお爺さんの座っていた席を眺めながら、私は詠唱を始めた。
お爺さんのような人が、ひとりもいないわけじゃない。
だから私は、砦の結界を超える魔族が絶対3歩ごとに躓く呪いをかけた。
あいつらも、憎くないわけじゃない。
それに、お爺さんは私が意地悪ばかりすると、悲しむからね。
それか死ぬ。
皺くちゃな可愛い手に、私のあげた薬草の袋を下げている。
「……」
「寂しそうな顔して。また仲直りできなかったのかい?」
「しないわ」
お爺さんを通り越して扉を開ける。
私はハッとして振り向いた。
「お茶とパイをごちそうさま、お爺さん。気をつけて帰ってね」
「ああ、また明日」
そう、お爺さんとは、こうでなくちゃ。
笑顔で手を振りあって、矍鑠とした背中を見送る。木こりのお爺さんは歳をとっても俊敏で、足腰がしっかりしていて、私が心配するような事は寿命しかない。
部屋に戻って、さっきまでお爺さんの座っていた席を眺めながら、私は詠唱を始めた。
お爺さんのような人が、ひとりもいないわけじゃない。
だから私は、砦の結界を超える魔族が絶対3歩ごとに躓く呪いをかけた。
あいつらも、憎くないわけじゃない。
それに、お爺さんは私が意地悪ばかりすると、悲しむからね。