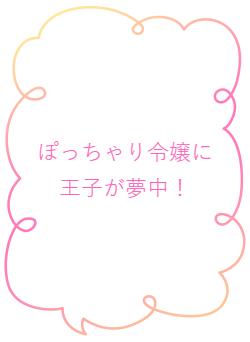「嫌よ」
「フレヤ」
「もう傷つきたくないわ……ッ、お爺さんがいるかわ私、少しずつ立ち直れたのに……っ」
だめだ。
もう、泣くモードから戻ってこれない。
「きっと立ち直る。そう信じて、フレヤとこうして過ごしているから、大丈夫だよ」
「おいていかないで……ッ」
「それは無理だ、フレヤ」
「わああぁぁぁっ」
ついに私は号泣した。
現実はあまりに無慈悲だ。
泣いている私を、お爺さんは優しい眼差しで静かに見守っていた。そして手を伸ばし、カップを握る私の指をそっと撫でた。ガザガザしたお爺さんの手が、いつか冷たくなってしまう。その日はそんなに、遠くない。
それでも平気だと、お爺さんは言う。
「えっ、えぐっ、うぅ」