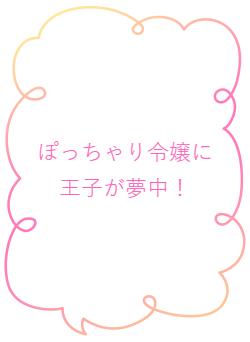わかっているのかボケているのか、お爺さんはハテナと首を傾げた。
私は今度こそ涙を止めて、しっかりと拭いて、気持ちを引き締めた。
噂が噂を呼んで魔女と呼ばれるようになった私の元には、ときどき身の程知らずの愚民どもがお忍びでやってくる。
私をけちょんけちょんに虐めておいて、助けを求めるなんて言語道断だ。
「フレヤ?」
席を立つと、お爺さんが心配そうな声をあげる。
「またお客さんかい?」
「ええ」
「あまり意地悪しちゃいけないよ」
「ええ。わかってるわお爺さん」
やり返すだけよ。
お爺さんは逞しいけど皺くちゃな指でカップを弄り、なにか言いたそうに眉を寄せて呻っている。
優しいお爺さん。
この世がお爺さんみたいな善い人ばかりだったらよかったのにね。