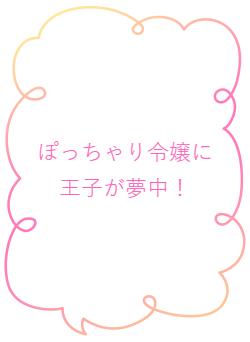「ごごごごめんなさいッ。私、もっとちゃんと……ッ」
「いいんだ。いいんだよ、フレヤ。そんな事は気にしなくていいんだ」
「だけど」
「フレヤ、フレヤ落ち着きなさい」
ふたりしてカップを置いて、呼吸を整える。
お爺さんの節くれだった手が、私を落ち着かせようひたすら掌で制してくる。
まあまあ。
どうどう。
「……あのね、お爺さん。私ね」
「ああ、わかったよ。聞いてあげるから、ゆっくり話てごらん」
「ええ、そうね」
胸を押さえて、上目遣いでお爺さんを見つめる。
お爺さんは、私から何が飛び出すかと、優しい顔に緊張を浮かべた。
私は、ついに、訊ねた。
「私、お爺さんの名前、聞いた?」
「……」
お爺さんはキョトンとしている。
「あのね。私、自分が名乗った記憶もその……曖昧なの」
「……」
お爺さんの目が、キュルンと上を向いた。
衰えた記憶力を総動員して、出会いの光景を思い描こうとしているようだ。