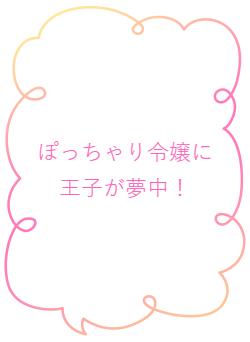「どうしたんだい、フレヤ。寂しそうな顔して」
「……っ」
午後のお茶にやってきたお爺さんが、そんな事を言うから、耐えていたものがワッと溢れて私は泣き崩れた。お爺さんはおろおろしながら私を椅子に座らせて、その前に両膝をついた。
「何か悲しい事があったんだね。話してごらん」
「うぅ、ぐっ、ひぐッ」
私は泣きながらフィリップ王子がいけしゃあしゃあとやって来た件を話した。
言いながら、悲しさと悔しさと情けなさがどんどん昂って、更に泣いた。
「うああぁぁぁっ」
「おお、よしよし。辛かったね」
「私が馬鹿だったのよ……ッ、あんなクソ野郎だったなんて……!」
「フレヤは馬鹿なんかじゃない。賢い、イイコだよ」
「嘘よぉッ! だって愛してたものッ!」
その感情を認めてしまったら、また次の波がこみ上げてきた。