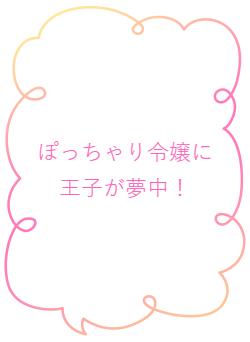「そんな事より風邪ひかないでよ。そうだ、関節痛に利く新しい調合を思いついたの。今のうちに10日くらい飲んで効果を試してみて」
「ありがとう、フレヤ。頂くよ」
焼き菓子を口に放り込むと、強めの風が窓を揺らした。
外へ目をやる私の顔を覗き込む、お爺さんが言った。
「ただの風だよ。大丈夫」
「ええ……、そうね」
追放されて、城壁の外の広い荒野へ放り出された日の記憶が蘇る。
忘れようとしても、忘れられない。
私にぶつけられた冷笑と侮蔑、罵倒。
杖も法衣も取り上げられて、卵や泥をぶつけられた。
罪人のように、石を投げられた。
痣を作って、血を流して。
涙が涸れるまで裸足で歩いた、あの荒野。
そっくりそのまま私の中に在り続ける、地獄の入り口。
どんなに朝を迎えても、どんなに優しい夢を見ても、風が私を引きずり戻す。
「フレヤ」
「……お爺さんはいいわね。大きいから飛ばされる心配もないし」
「ほら、焼き菓子をお食べ。こっちを見るんだ、いい子だから」
空を睨む私の前に、お爺さんが焼き菓子を摘まんで見せる。
その皺くちゃだけど太くて頑丈な指を見ていると、自分が酷く醜く思えてくる。
「……」
悔しい。
許せない。
子供みたいに口を開けて、お爺さんのくれる焼き菓子を無邪気に食べられたらいいのに。でも私の唇も、歯も、喉も、怨嗟を吐き出さないように固く鎖されている。
泣かないように、鼻で深呼吸を繰り返した。
お爺さんは焼き菓子を持つ手を下げて、少し考えてから、自分で食べた。
「……」
「ありがとう、フレヤ。頂くよ」
焼き菓子を口に放り込むと、強めの風が窓を揺らした。
外へ目をやる私の顔を覗き込む、お爺さんが言った。
「ただの風だよ。大丈夫」
「ええ……、そうね」
追放されて、城壁の外の広い荒野へ放り出された日の記憶が蘇る。
忘れようとしても、忘れられない。
私にぶつけられた冷笑と侮蔑、罵倒。
杖も法衣も取り上げられて、卵や泥をぶつけられた。
罪人のように、石を投げられた。
痣を作って、血を流して。
涙が涸れるまで裸足で歩いた、あの荒野。
そっくりそのまま私の中に在り続ける、地獄の入り口。
どんなに朝を迎えても、どんなに優しい夢を見ても、風が私を引きずり戻す。
「フレヤ」
「……お爺さんはいいわね。大きいから飛ばされる心配もないし」
「ほら、焼き菓子をお食べ。こっちを見るんだ、いい子だから」
空を睨む私の前に、お爺さんが焼き菓子を摘まんで見せる。
その皺くちゃだけど太くて頑丈な指を見ていると、自分が酷く醜く思えてくる。
「……」
悔しい。
許せない。
子供みたいに口を開けて、お爺さんのくれる焼き菓子を無邪気に食べられたらいいのに。でも私の唇も、歯も、喉も、怨嗟を吐き出さないように固く鎖されている。
泣かないように、鼻で深呼吸を繰り返した。
お爺さんは焼き菓子を持つ手を下げて、少し考えてから、自分で食べた。
「……」