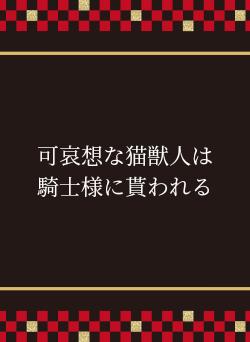畳み掛けるように確かめられ、リアの頬が一拍遅れて熱くなる。
何てことを言うのだろう。こんな貴公子に「会いに行く」なんて言われた女性は皆勘違いしてしまうのではなかろうか──エドウィンがそれを望んでいるとは露知らず、リアは全くまとまっていない思考を口から吐き出した。
「い、いけないことはないけど、いや、でもエルヴァスティよ? とっても遠いし」
「帝国へ渡るついでなら、然して距離も感じません」
「大公様の許可とか」
「僕自身と大公国のためにも、精霊に関する知識を蓄えよと仰せでした」
「あう……そ、そっか……じゃあ問題ないのかしら」
「ええ。あとはリアが許してくれれば、気兼ねなく東へ向かえるのですが」
自分の許可は必要ないのでは、とリアは困惑する。しかし目の前で恭しく手をすくう麗しい貴公子は、こちらの許しを真摯に待っている。
むず痒さを覚えつつも彼の手と瞳を交互に見詰め、リアはやがて小刻みに頷いた。
「その……これからもエドウィンに会えるなら、嬉しいわ。エルヴァスティで待ってるね」
素直な気持ちを明かせば、菫色の瞳が甘くとろける。まるで飴を溶かしたようだと、リアがわけもなく疼いた胸元を押さえたとき。
うつむきがちだった顎をそっと摘まれたかと思えば、前髪を避けた額にやわらかく唇が押し付けられる。
ほんの一瞬の出来事だったが、リアの全身を発熱させるには十分すぎた。今度こそ心臓が激しく暴れるままに奇声を上げてしまった彼女は、慌ただしく後背の階段に崩れ落ちる。
「ひょわぁ!? なななな何?!」
「すみません、嬉しかったので思わず」
「思わず!? も、もう、大袈裟よ! やっぱり都会の男は油断ならないわ!」
おかしげに笑うエドウィンに頬を膨らませたリアは、手早く荷物を抱えて彼の脇をすり抜けた。屋敷の扉を肩で押し開けては、朱を引きずった顔で振り返り。
「またねエドウィン!」
「はい。また……今度はあなたの故郷で」
最後には笑顔で再会の約束をして、外で待つ師匠の元へ駆けたのだった。
何てことを言うのだろう。こんな貴公子に「会いに行く」なんて言われた女性は皆勘違いしてしまうのではなかろうか──エドウィンがそれを望んでいるとは露知らず、リアは全くまとまっていない思考を口から吐き出した。
「い、いけないことはないけど、いや、でもエルヴァスティよ? とっても遠いし」
「帝国へ渡るついでなら、然して距離も感じません」
「大公様の許可とか」
「僕自身と大公国のためにも、精霊に関する知識を蓄えよと仰せでした」
「あう……そ、そっか……じゃあ問題ないのかしら」
「ええ。あとはリアが許してくれれば、気兼ねなく東へ向かえるのですが」
自分の許可は必要ないのでは、とリアは困惑する。しかし目の前で恭しく手をすくう麗しい貴公子は、こちらの許しを真摯に待っている。
むず痒さを覚えつつも彼の手と瞳を交互に見詰め、リアはやがて小刻みに頷いた。
「その……これからもエドウィンに会えるなら、嬉しいわ。エルヴァスティで待ってるね」
素直な気持ちを明かせば、菫色の瞳が甘くとろける。まるで飴を溶かしたようだと、リアがわけもなく疼いた胸元を押さえたとき。
うつむきがちだった顎をそっと摘まれたかと思えば、前髪を避けた額にやわらかく唇が押し付けられる。
ほんの一瞬の出来事だったが、リアの全身を発熱させるには十分すぎた。今度こそ心臓が激しく暴れるままに奇声を上げてしまった彼女は、慌ただしく後背の階段に崩れ落ちる。
「ひょわぁ!? なななな何?!」
「すみません、嬉しかったので思わず」
「思わず!? も、もう、大袈裟よ! やっぱり都会の男は油断ならないわ!」
おかしげに笑うエドウィンに頬を膨らませたリアは、手早く荷物を抱えて彼の脇をすり抜けた。屋敷の扉を肩で押し開けては、朱を引きずった顔で振り返り。
「またねエドウィン!」
「はい。また……今度はあなたの故郷で」
最後には笑顔で再会の約束をして、外で待つ師匠の元へ駆けたのだった。