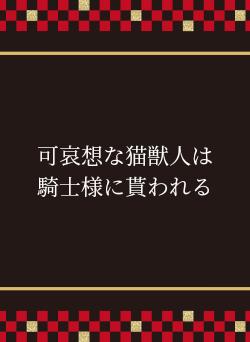クルサード帝国の次期皇帝サディアス。
現皇帝シルヴェスタ―が病に伏しがちな昨今、政務の大半は既に皇太子が引き継いでおり、この調子なら即位も間近であろうと各所で噂されている。
しかしながらこの皇太子、つい数年前までとんでもない問題児として名を馳せていた。
幼い頃、侍女に用意させたウィッグを装着し、平民の子どもに紛れては泥遊びに耽ったり。
公的な催しに影武者を立て、自身は図書館で一人爆睡していたり。
他国の来賓に剣の手合わせを申し込まれたときは、周囲から散々「接待ですからね」と注意されたにも関わらず、立ち上がれなくなるほど叩きのめしたり。
皇太子としては些かやんちゃが過ぎる彼だったが、年齢を経るごとに相応の落ち着きを見せ始め、祖父である皇帝を含め皆が安心した──はずだった。
「──オーレリア、そんなに逃げなくても。僕とお前の仲だろう」
「ひええええ!! もう嫌だ、何で貴族はみんな素性を隠して近付いてくるの!? 富裕層の遊びなの!?」
ムイヤールを始めとする教会の者たちがとぼとぼと退室して暫くのち。
エドウィンを盾にしつつ部屋の端っこまで後退したリアは、ここ最近で何度も経験した焦りと腹痛に苛まれつつ叫んだ。彼女の反応がいたく面白かったのか、当の皇太子は「ほら出ておいで」と犬を誘き寄せるかのように手を広げている。
二人の間で壁になっていたエドウィンは、頬を引き攣らせながらもリアに声を掛けた。
「リア、サディアス殿下は日頃からその……他人を驚かせることがお好きなので、そこまで怯えずとも大丈夫かと」
「卿の言う通り。そもそも平民に一発でバレるような変装じゃ意味がない」
「……しかし殿下、何故メイスフィールドまで?」
「ん? 西方教会の司教が暴走していると聞いて、遥々やって来たんだよ」
今頃、宿に置いてきた護衛騎士が慌てふためいていることだろうと、サディアスは無慈悲な笑声を上げる。
それはともかくとして、皇太子はムイヤール司教が大公家の地位を貶めようとしている動きを察知し、以前からその動向を監視していたそうだ。大公家で立て続けに起きている不審死の原因が精霊によるものだという主張は、再び世間に混乱を招くと同時に──新たな火種を生む可能性があったとサディアスは語る。
「オルブライト家が暴徒化した民衆によって打倒されて、その末ここが教皇領にでもなれば我々皇帝派の力は弱まる。そんな状態で奴らがエルヴァスティに攻め入ったら、さすがに止めようがなくなるからね」
「どぇ!? そこでどうしてエルヴァスティが出てくるんですか」
「イーリル教会はかの国をそれはそれは敵対視してるみたいだよ。例の如くユスティーナ女史からは全く相手にされてないけど」
つまるところ教会は、精霊の影が見え隠れする大公家を公の場で弾劾し、君主を排除したメイスフィールドを教皇の支配下に置くつもりだったのだ。そうして得られた戦力をもってして、イーリル教とは相容れない価値観や思想を持つエルヴァスティを攻め落とさんと目論んでいた、と。
危うく故郷が戦火に晒されるところだったのかと、リアはぞっとしてしまった。同時に、そんな事態を防ぐためにサディアスが動いてくれていたことに、感謝してもしきれない。
「そ、そんなことになってたなんて……」
「……だから彼らの前でわざわざ、僕とリアの名前を出して命じられたのですね」
「そうだね。大公家の問題解決は、その当事者と専門家に任せるべきだろう?」
教会が大公家の秘密を探り始めた以上、今まで通りの知らん振りは得策ではない。だからこそ皇太子であるサディアスが不審死の解明に踏切ることで、教会が勝手な真似──例えば魔女狩りのような強引で不条理な取り調べが出来ぬよう、大公家の調査権を握ったのだ。
リアとエドウィン、すなわちエルヴァスティとメイスフィールドという、教会が狙う二つの国が協力し合うことまで実現させつつ。
「魔女狩りでは陛下が随分と苦労されたから、二の舞は避けなくちゃね」
「凄い、本当に皇太子様みたいなこと言ってるわ」
「リア、彼は間違いなく皇太子ですよ」
不敬罪待ったなしの失言を、エドウィンがそっと覆い隠す。二人のやり取りを特に気にした様子もなく、サディアスはやはり呑気に笑っていた。
しかし皇太子の行動に理解は及んだものの、リアには今一つ分からないことが。
「ねえアスラン……じゃなかった、サディアス様」
「何?」
「いつ私が精霊術師だと分かったんですか?」
「司教が来る前に、ゼルフォード卿に石を渡してたでしょ。あのときに確信したよ」
ということは、アミュレットを見たことがあったのだろうか。目を瞬かせてエドウィンを見遣れば、彼も少し驚いたように自身の胸元──そこで淡く光るロケットを一瞥した。
「殿下もアミュレットを頂いたことがおありで?」
「昔ね」
説明はたったそれだけだったが、サディアスの瞳はどこか遠かった。アミュレットを貰った相手に思いを馳せているのか、その口元に曖昧な笑みを刻んで。
やがて皇太子は二人の窺うような視線に気付き、にこりと唇の端を吊り上げる。
「というわけで、作戦会議に入ろうか。……陛下から伺った昔話も添えながらね」
現皇帝シルヴェスタ―が病に伏しがちな昨今、政務の大半は既に皇太子が引き継いでおり、この調子なら即位も間近であろうと各所で噂されている。
しかしながらこの皇太子、つい数年前までとんでもない問題児として名を馳せていた。
幼い頃、侍女に用意させたウィッグを装着し、平民の子どもに紛れては泥遊びに耽ったり。
公的な催しに影武者を立て、自身は図書館で一人爆睡していたり。
他国の来賓に剣の手合わせを申し込まれたときは、周囲から散々「接待ですからね」と注意されたにも関わらず、立ち上がれなくなるほど叩きのめしたり。
皇太子としては些かやんちゃが過ぎる彼だったが、年齢を経るごとに相応の落ち着きを見せ始め、祖父である皇帝を含め皆が安心した──はずだった。
「──オーレリア、そんなに逃げなくても。僕とお前の仲だろう」
「ひええええ!! もう嫌だ、何で貴族はみんな素性を隠して近付いてくるの!? 富裕層の遊びなの!?」
ムイヤールを始めとする教会の者たちがとぼとぼと退室して暫くのち。
エドウィンを盾にしつつ部屋の端っこまで後退したリアは、ここ最近で何度も経験した焦りと腹痛に苛まれつつ叫んだ。彼女の反応がいたく面白かったのか、当の皇太子は「ほら出ておいで」と犬を誘き寄せるかのように手を広げている。
二人の間で壁になっていたエドウィンは、頬を引き攣らせながらもリアに声を掛けた。
「リア、サディアス殿下は日頃からその……他人を驚かせることがお好きなので、そこまで怯えずとも大丈夫かと」
「卿の言う通り。そもそも平民に一発でバレるような変装じゃ意味がない」
「……しかし殿下、何故メイスフィールドまで?」
「ん? 西方教会の司教が暴走していると聞いて、遥々やって来たんだよ」
今頃、宿に置いてきた護衛騎士が慌てふためいていることだろうと、サディアスは無慈悲な笑声を上げる。
それはともかくとして、皇太子はムイヤール司教が大公家の地位を貶めようとしている動きを察知し、以前からその動向を監視していたそうだ。大公家で立て続けに起きている不審死の原因が精霊によるものだという主張は、再び世間に混乱を招くと同時に──新たな火種を生む可能性があったとサディアスは語る。
「オルブライト家が暴徒化した民衆によって打倒されて、その末ここが教皇領にでもなれば我々皇帝派の力は弱まる。そんな状態で奴らがエルヴァスティに攻め入ったら、さすがに止めようがなくなるからね」
「どぇ!? そこでどうしてエルヴァスティが出てくるんですか」
「イーリル教会はかの国をそれはそれは敵対視してるみたいだよ。例の如くユスティーナ女史からは全く相手にされてないけど」
つまるところ教会は、精霊の影が見え隠れする大公家を公の場で弾劾し、君主を排除したメイスフィールドを教皇の支配下に置くつもりだったのだ。そうして得られた戦力をもってして、イーリル教とは相容れない価値観や思想を持つエルヴァスティを攻め落とさんと目論んでいた、と。
危うく故郷が戦火に晒されるところだったのかと、リアはぞっとしてしまった。同時に、そんな事態を防ぐためにサディアスが動いてくれていたことに、感謝してもしきれない。
「そ、そんなことになってたなんて……」
「……だから彼らの前でわざわざ、僕とリアの名前を出して命じられたのですね」
「そうだね。大公家の問題解決は、その当事者と専門家に任せるべきだろう?」
教会が大公家の秘密を探り始めた以上、今まで通りの知らん振りは得策ではない。だからこそ皇太子であるサディアスが不審死の解明に踏切ることで、教会が勝手な真似──例えば魔女狩りのような強引で不条理な取り調べが出来ぬよう、大公家の調査権を握ったのだ。
リアとエドウィン、すなわちエルヴァスティとメイスフィールドという、教会が狙う二つの国が協力し合うことまで実現させつつ。
「魔女狩りでは陛下が随分と苦労されたから、二の舞は避けなくちゃね」
「凄い、本当に皇太子様みたいなこと言ってるわ」
「リア、彼は間違いなく皇太子ですよ」
不敬罪待ったなしの失言を、エドウィンがそっと覆い隠す。二人のやり取りを特に気にした様子もなく、サディアスはやはり呑気に笑っていた。
しかし皇太子の行動に理解は及んだものの、リアには今一つ分からないことが。
「ねえアスラン……じゃなかった、サディアス様」
「何?」
「いつ私が精霊術師だと分かったんですか?」
「司教が来る前に、ゼルフォード卿に石を渡してたでしょ。あのときに確信したよ」
ということは、アミュレットを見たことがあったのだろうか。目を瞬かせてエドウィンを見遣れば、彼も少し驚いたように自身の胸元──そこで淡く光るロケットを一瞥した。
「殿下もアミュレットを頂いたことがおありで?」
「昔ね」
説明はたったそれだけだったが、サディアスの瞳はどこか遠かった。アミュレットを貰った相手に思いを馳せているのか、その口元に曖昧な笑みを刻んで。
やがて皇太子は二人の窺うような視線に気付き、にこりと唇の端を吊り上げる。
「というわけで、作戦会議に入ろうか。……陛下から伺った昔話も添えながらね」