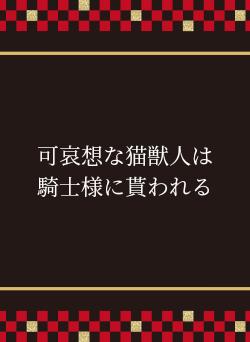二頭蛇の杖が分厚い布に包まれていく様を、イヴァンは静かに眺めていた。
それは故郷に伝わる秘宝であると同時に、彼にとって己の地位を確かなものにする唯一の証だった。顔も知らぬ父親から譲り受けた、キーシンの王を自称するための。
「本当に良かったのかい、イヴァン王子」
宝物庫から視線を外して振り返ると、皇太子の姿がそこにある。鳶色の瞳でモーセルの杖を一瞥すると、改めて問いかけるように眉を動かす。
イヴァンは然して動じることもなく、ひとつ肯いて了承の意を示した。
「あの杖も、王位も、俺の手には余る。帝国とエルヴァスティの連中で管理してくれるなら、それが最善だと判断したまでだ」
「聖遺物、だったかな? 確かに人が触っていいもんじゃないね」
件の大罪人の末路を思い浮かべてか、サディアスは肩を竦める。
キーシンの民を散々振り回してくれた男は、数日前に命を落とした。聞けば、彼は最愛の妻を蘇らせるためだけに、イヴァンやその配下に近付いたのだという。禍を支配する杖──聖遺物の存在を何処かから嗅ぎつけて。
今後、ダグラスのような輩が二度と出てこないとは断言できない。聖遺物という呼び名に惹かれ、よからぬことを考える者も現れることだろう。
そうなったとき、国と民を持たぬ王なんぞに、モーセルの杖を守り切るほどの力はない。
イヴァンは刺青の刻まれた自身の手を見詰め、鷹揚な動きで踵を返した。
「サディアス皇太子。長いこと迷惑を掛けたな。俺の首を城門に晒せば、下らん戦は終わりだ」
「ん? ああ、そのことなんだけど」
サディアスは今思い出したと手を打ち、静まり返った回廊を振り返る。釣られて見てみれば、脇の通路から小さな頭がいくつもこちらを覗いていた。
キーシンの戦災孤児たちだ。彼らの纏う清潔な衣類や、綺麗に洗われた髪や肌を見るに、手厚く扱われていることが窺える。知らずの内に安堵の息を漏らしていたイヴァンの耳に、皇太子の笑い交じりの声が届く。
「彼らの保護者が必要でね。引き取り先が決まるまで預かってくれるかい、というかもう決まったから返事は要らないよ」
「は?」
「そうそう、エルヴァスティの天才ことリュカ・フルメヴァーラ術師からも口添えがあってね」
はい、と気軽に差し出された紙切れ。手帳から適当に切り取ったような小さなそれを、イヴァンは怪訝な表情で受け取る。そこにはやはり、食事でもしながら片手間に書いたであろう文字が斜めに並んでいた。
──おじちゃん、今度薬草の採取するから手伝って。
あのガキか──完全に乗り物扱いされているイヴァンが頭を抱えれば、一方の皇太子は朗笑を上げる。
「勝利宣言に使う首は、勝手に首長を名乗っているあの男にするよ。貴殿はキーシンの未来のため、しばらく力を貸してくれると嬉しいな」
「未来?」
「言っただろう? キーシンの文化はこれからも受け継ぐつもりさ」
イヴァンが何かを言うより先に、話は終わったと言わんばかりにサディアスは背を向けてしまう。それが合図だったのか、うずうずと飛び出す機会を窺っていた子どもたちが「イヴァン様!」と駆けてきた。
彼らの勢いある突進を受け止めつつ、イヴァンは微苦笑をこぼしたのだった。
それは故郷に伝わる秘宝であると同時に、彼にとって己の地位を確かなものにする唯一の証だった。顔も知らぬ父親から譲り受けた、キーシンの王を自称するための。
「本当に良かったのかい、イヴァン王子」
宝物庫から視線を外して振り返ると、皇太子の姿がそこにある。鳶色の瞳でモーセルの杖を一瞥すると、改めて問いかけるように眉を動かす。
イヴァンは然して動じることもなく、ひとつ肯いて了承の意を示した。
「あの杖も、王位も、俺の手には余る。帝国とエルヴァスティの連中で管理してくれるなら、それが最善だと判断したまでだ」
「聖遺物、だったかな? 確かに人が触っていいもんじゃないね」
件の大罪人の末路を思い浮かべてか、サディアスは肩を竦める。
キーシンの民を散々振り回してくれた男は、数日前に命を落とした。聞けば、彼は最愛の妻を蘇らせるためだけに、イヴァンやその配下に近付いたのだという。禍を支配する杖──聖遺物の存在を何処かから嗅ぎつけて。
今後、ダグラスのような輩が二度と出てこないとは断言できない。聖遺物という呼び名に惹かれ、よからぬことを考える者も現れることだろう。
そうなったとき、国と民を持たぬ王なんぞに、モーセルの杖を守り切るほどの力はない。
イヴァンは刺青の刻まれた自身の手を見詰め、鷹揚な動きで踵を返した。
「サディアス皇太子。長いこと迷惑を掛けたな。俺の首を城門に晒せば、下らん戦は終わりだ」
「ん? ああ、そのことなんだけど」
サディアスは今思い出したと手を打ち、静まり返った回廊を振り返る。釣られて見てみれば、脇の通路から小さな頭がいくつもこちらを覗いていた。
キーシンの戦災孤児たちだ。彼らの纏う清潔な衣類や、綺麗に洗われた髪や肌を見るに、手厚く扱われていることが窺える。知らずの内に安堵の息を漏らしていたイヴァンの耳に、皇太子の笑い交じりの声が届く。
「彼らの保護者が必要でね。引き取り先が決まるまで預かってくれるかい、というかもう決まったから返事は要らないよ」
「は?」
「そうそう、エルヴァスティの天才ことリュカ・フルメヴァーラ術師からも口添えがあってね」
はい、と気軽に差し出された紙切れ。手帳から適当に切り取ったような小さなそれを、イヴァンは怪訝な表情で受け取る。そこにはやはり、食事でもしながら片手間に書いたであろう文字が斜めに並んでいた。
──おじちゃん、今度薬草の採取するから手伝って。
あのガキか──完全に乗り物扱いされているイヴァンが頭を抱えれば、一方の皇太子は朗笑を上げる。
「勝利宣言に使う首は、勝手に首長を名乗っているあの男にするよ。貴殿はキーシンの未来のため、しばらく力を貸してくれると嬉しいな」
「未来?」
「言っただろう? キーシンの文化はこれからも受け継ぐつもりさ」
イヴァンが何かを言うより先に、話は終わったと言わんばかりにサディアスは背を向けてしまう。それが合図だったのか、うずうずと飛び出す機会を窺っていた子どもたちが「イヴァン様!」と駆けてきた。
彼らの勢いある突進を受け止めつつ、イヴァンは微苦笑をこぼしたのだった。