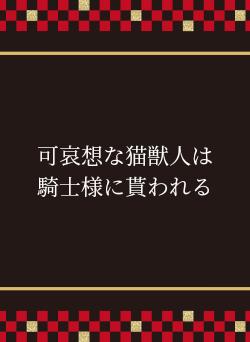目を覚ましたリアは、狭い洞窟に一人立ち尽くしていた。
朽ちた支柱と冷え切った土のみで構成された空間。どことなく見覚えのある景色に足が竦むも、彼女の後ろに引き返せそうな道はない。低く唸る風穴の奥へ進むしか、ここから抜け出す術はないように思えた。
全くもって気乗りしないまま、リアは恐る恐る洞窟を歩き始める。
「……私、どうなったんだっけ。真っ黒な穴に落ちて、それから……」
ダグラスの術に嵌まり、深い穴に落ちてからの記憶がどうにも曖昧だ。影の精霊に備わっていると見られる転移の力で、先程の森とは異なる場所に連れて来られてしまったのだろうか。
それか今見ている景色が現実のものではなく、影の精霊が創り出した幻覚という線も──。
リアは無意識のうちに速めていた足をぴたりと止める。
呼吸の音さえも最小限に抑えて、進路の先から運ばれてくる微かな物音に耳を澄ませた。
……衣擦れかと思ったが、足音らしきものは聞こえない。
何か長大なものをゆっくりと、延々と引き摺っているような。
忍び足で前へ進みながら、リアは段々と近付く四角い梁を注視した。
暗く狭い通路の終わりを告げる門だというのに、素直な喜びよりも不安が勝る。あの梁をくぐったら、何か恐ろしいことが身に降りかかるのではないかと、異常な緊張がリアの手に汗を滲ませた。
そしていよいよ梁が目前にまで迫ったとき、淡く発光する白が鼻先を掠める。
「え……」
喉が引き攣り、ざわりと全身が総毛立つ。
──蛇だ。
人間の背丈を優に超える白蛇の、瓦状に連なった無数の鱗が、梁の向こうでずるずると動いている。
そこでリアはようやく、この不気味な洞窟と巨大な白蛇を何度も夢に見ていたことを思い出してしまった。
朝、目を覚ますたびに跡形もなく消えてしまうくせに、正体の分からぬ恐怖と不快感だけをリアに残していく、とても嫌な夢。
浅い呼吸を繰り返しているうちに、気付けば白蛇の頭がこちらを見ていた。開かれた細長い瞳孔が瞬き、分かれた舌がちろりと覗く。
何もかもが悪夢と同じだ。リアは恐怖で動けなくなり、悲鳴を上げることも出来ぬまま呆気なく蛇の胃袋に収まってしまうことだろう。
ぎゅっと目を瞑り、訪れる痛みに備えて体を縮めたリアは、しかして一向に動かない気配に戸惑う。そうっと瞼を押し開いてみると、蛇はおもむろに頭部を伸ばして近付いてきた。
「ひっ」
今度こそ駄目だとその場に屈んだのも束の間、丸まった背中を滑らかな顎で撫でられる。
次にぐいぐいと脇腹を押されたかと思えば、体が横転した。ごろごろと後ろへ転がされてしまい、リアは来た道に押し戻されながら叫ぶ。
「ちょっと何!? ゆ、夢と違う……!?」
ある程度リアを転がして下がらせると、蛇は満足したのか顎を離した。そのまま静々と梁の奥へ引っ込んでいこうとする白蛇に、リアは声に混乱を乗せて呼び掛ける。
「ねぇ! ここは何なのっ? どうやったら外に出られぅぎゃあ!? ごめんなさい近付かないからこっち来ないで!」
ちょっとでも前へ出ようものなら、蛇がまたもやリアを押し戻そうとする。にゅっと寄ってきた白い顔に慄きながら後退した彼女は、一呼吸置いてから躊躇いがちに尋ねた。
「……そこに、入っちゃいけないのね? あなた、もしかして──夢の中で何度も私を追い返していたの?」
この大きな白蛇は、自分が思い込んでいるほど邪悪な存在ではないのかもしれない。
悪夢の中でだって、蛇はいつも同じ場所でリアを喰らう素振りを見せ──彼女を悪夢から無理やり追い出していたようにも思える。
まるで、この先へ来てはならないと警告するかのように。
いわば白蛇は、洞窟の奥にある何かを守る者なのだろう。
入るなと言われている以上確かめることは出来ないが、この推測はあながち間違っていない気がした。とは言え長年の苦手意識が簡単に払拭されるわけでもなし。リアは質問もほどほどに、大人しく引き返そうかと思ったのだが。
「うわっ」
ぐらりと洞窟全体が震動し、岩壁に肩を打ち付ける。
尋常ではない揺れに怯える暇もなく、身の危険を感じたリアは咄嗟に地を蹴った。だがこのまま引き返したところで行き止まりにぶち当たってしまう。どうにかして洞窟の出口を探さなければと、忙しなく視線を動かしたときだった。
一本道だったはずの通路から細い脇道が伸びていることに気付いたリアは、爪先を急転換してそこへ駈け込む。
見通しの悪い視界を全力で走っていくと、通路のあらゆる壁から影が滲みだした。
やはり影の精霊の領域だったかと焦る一方で、脇道に入ったリアを引き留めるように出現したところを見るに、このまま迷わず進むべきだという確信が同時に芽生える。
「どいてっ、私は供物なんかにならないわよ! 絶っ対に生きて帰ってやる!!」
張り上げた声は影の精霊への威嚇であり、己を奮い立てるための誓いだったが──それに乗じてもう一つ、リアの声に呼応したものがあった。
右耳で揺れる紫水晶が光を帯び、次第にその輝きを強めていく。リアが前へ進めば進むだけ、耳飾りから美しい雫が溢れ滴る。
──近くにいる。
そう直感したとき、意図せず瞳から涙がこぼれた。
洞窟の景色すら塗り潰された漆黒の中、挫けずに足を動かし続けたリアは、突如として現れた光の中へと大きく踏み切る。
「リア!!」
眩い光と共にリアを迎えたのは、こちらに腕を伸ばすエドウィンだった。
宙を掻いた両手がすかさず掴まれ、体ごと力強く引き寄せられる。咄嗟に逞しい肩にしがみついたところで、二人は硬い石畳に倒れ込んだのだった。
朽ちた支柱と冷え切った土のみで構成された空間。どことなく見覚えのある景色に足が竦むも、彼女の後ろに引き返せそうな道はない。低く唸る風穴の奥へ進むしか、ここから抜け出す術はないように思えた。
全くもって気乗りしないまま、リアは恐る恐る洞窟を歩き始める。
「……私、どうなったんだっけ。真っ黒な穴に落ちて、それから……」
ダグラスの術に嵌まり、深い穴に落ちてからの記憶がどうにも曖昧だ。影の精霊に備わっていると見られる転移の力で、先程の森とは異なる場所に連れて来られてしまったのだろうか。
それか今見ている景色が現実のものではなく、影の精霊が創り出した幻覚という線も──。
リアは無意識のうちに速めていた足をぴたりと止める。
呼吸の音さえも最小限に抑えて、進路の先から運ばれてくる微かな物音に耳を澄ませた。
……衣擦れかと思ったが、足音らしきものは聞こえない。
何か長大なものをゆっくりと、延々と引き摺っているような。
忍び足で前へ進みながら、リアは段々と近付く四角い梁を注視した。
暗く狭い通路の終わりを告げる門だというのに、素直な喜びよりも不安が勝る。あの梁をくぐったら、何か恐ろしいことが身に降りかかるのではないかと、異常な緊張がリアの手に汗を滲ませた。
そしていよいよ梁が目前にまで迫ったとき、淡く発光する白が鼻先を掠める。
「え……」
喉が引き攣り、ざわりと全身が総毛立つ。
──蛇だ。
人間の背丈を優に超える白蛇の、瓦状に連なった無数の鱗が、梁の向こうでずるずると動いている。
そこでリアはようやく、この不気味な洞窟と巨大な白蛇を何度も夢に見ていたことを思い出してしまった。
朝、目を覚ますたびに跡形もなく消えてしまうくせに、正体の分からぬ恐怖と不快感だけをリアに残していく、とても嫌な夢。
浅い呼吸を繰り返しているうちに、気付けば白蛇の頭がこちらを見ていた。開かれた細長い瞳孔が瞬き、分かれた舌がちろりと覗く。
何もかもが悪夢と同じだ。リアは恐怖で動けなくなり、悲鳴を上げることも出来ぬまま呆気なく蛇の胃袋に収まってしまうことだろう。
ぎゅっと目を瞑り、訪れる痛みに備えて体を縮めたリアは、しかして一向に動かない気配に戸惑う。そうっと瞼を押し開いてみると、蛇はおもむろに頭部を伸ばして近付いてきた。
「ひっ」
今度こそ駄目だとその場に屈んだのも束の間、丸まった背中を滑らかな顎で撫でられる。
次にぐいぐいと脇腹を押されたかと思えば、体が横転した。ごろごろと後ろへ転がされてしまい、リアは来た道に押し戻されながら叫ぶ。
「ちょっと何!? ゆ、夢と違う……!?」
ある程度リアを転がして下がらせると、蛇は満足したのか顎を離した。そのまま静々と梁の奥へ引っ込んでいこうとする白蛇に、リアは声に混乱を乗せて呼び掛ける。
「ねぇ! ここは何なのっ? どうやったら外に出られぅぎゃあ!? ごめんなさい近付かないからこっち来ないで!」
ちょっとでも前へ出ようものなら、蛇がまたもやリアを押し戻そうとする。にゅっと寄ってきた白い顔に慄きながら後退した彼女は、一呼吸置いてから躊躇いがちに尋ねた。
「……そこに、入っちゃいけないのね? あなた、もしかして──夢の中で何度も私を追い返していたの?」
この大きな白蛇は、自分が思い込んでいるほど邪悪な存在ではないのかもしれない。
悪夢の中でだって、蛇はいつも同じ場所でリアを喰らう素振りを見せ──彼女を悪夢から無理やり追い出していたようにも思える。
まるで、この先へ来てはならないと警告するかのように。
いわば白蛇は、洞窟の奥にある何かを守る者なのだろう。
入るなと言われている以上確かめることは出来ないが、この推測はあながち間違っていない気がした。とは言え長年の苦手意識が簡単に払拭されるわけでもなし。リアは質問もほどほどに、大人しく引き返そうかと思ったのだが。
「うわっ」
ぐらりと洞窟全体が震動し、岩壁に肩を打ち付ける。
尋常ではない揺れに怯える暇もなく、身の危険を感じたリアは咄嗟に地を蹴った。だがこのまま引き返したところで行き止まりにぶち当たってしまう。どうにかして洞窟の出口を探さなければと、忙しなく視線を動かしたときだった。
一本道だったはずの通路から細い脇道が伸びていることに気付いたリアは、爪先を急転換してそこへ駈け込む。
見通しの悪い視界を全力で走っていくと、通路のあらゆる壁から影が滲みだした。
やはり影の精霊の領域だったかと焦る一方で、脇道に入ったリアを引き留めるように出現したところを見るに、このまま迷わず進むべきだという確信が同時に芽生える。
「どいてっ、私は供物なんかにならないわよ! 絶っ対に生きて帰ってやる!!」
張り上げた声は影の精霊への威嚇であり、己を奮い立てるための誓いだったが──それに乗じてもう一つ、リアの声に呼応したものがあった。
右耳で揺れる紫水晶が光を帯び、次第にその輝きを強めていく。リアが前へ進めば進むだけ、耳飾りから美しい雫が溢れ滴る。
──近くにいる。
そう直感したとき、意図せず瞳から涙がこぼれた。
洞窟の景色すら塗り潰された漆黒の中、挫けずに足を動かし続けたリアは、突如として現れた光の中へと大きく踏み切る。
「リア!!」
眩い光と共にリアを迎えたのは、こちらに腕を伸ばすエドウィンだった。
宙を掻いた両手がすかさず掴まれ、体ごと力強く引き寄せられる。咄嗟に逞しい肩にしがみついたところで、二人は硬い石畳に倒れ込んだのだった。