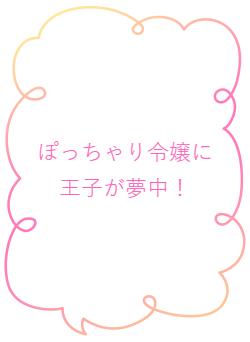ひどく場違いな気がして、居た堪れなくてがっくりと俯いた。
食事?
そんなもの、どんなに美味しくたって喉を通らない。
気分転換に器械体操しまくりで、体は引き締まる一方だ。
でもそんなもの、意味がない。
価値もない。
私なんて、いなくなったって、きっとわからない。
壁の花どころか、むしろ壁。
「あっ」
「?」
近くを通りかかった給仕役の少女がバランスを崩した。咄嗟に手を出して支える。持っていたカトラリーが私のドレスで衝撃を和らげて、静かに床に落ちた。
「あ、あ、も、申し訳ございません……ッ!」
食事?
そんなもの、どんなに美味しくたって喉を通らない。
気分転換に器械体操しまくりで、体は引き締まる一方だ。
でもそんなもの、意味がない。
価値もない。
私なんて、いなくなったって、きっとわからない。
壁の花どころか、むしろ壁。
「あっ」
「?」
近くを通りかかった給仕役の少女がバランスを崩した。咄嗟に手を出して支える。持っていたカトラリーが私のドレスで衝撃を和らげて、静かに床に落ちた。
「あ、あ、も、申し訳ございません……ッ!」