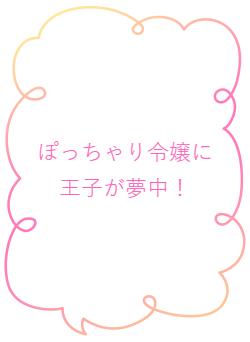そうしてふたりで同じ星空を見あげているのが、とても、幸せだと気づく。
「あの美しい星々のすべてが俺は好きだ。もし俺にその力があるのなら、あの輝きを守りたい。あの光をたくさんの人に届けたい。だが俺のものではない。空を、星を、独り占めにしたいなどとは思わない」
「みんなに愛されるべきものだから」
「そうだ。でもたったひとつだけ、どうしても欲しい星があった。それがお前だ」
「……」
涙が零れた。
唐突に、わかったのだ。
私は愛されている。
今までも、たぶん、愛されていたのだと。
「俺はお前が好きだ。ダリヤ、お前は、俺が好きか?」
顎の下で交差するバスィーム王子の腕に指をかけて、私は答えた。
「はい」
星空の下で交わされたキスを、私は一生忘れないだろう。
私をかけがえのない存在だと教えてくれた、愛しい人の眼差しも。
「あの美しい星々のすべてが俺は好きだ。もし俺にその力があるのなら、あの輝きを守りたい。あの光をたくさんの人に届けたい。だが俺のものではない。空を、星を、独り占めにしたいなどとは思わない」
「みんなに愛されるべきものだから」
「そうだ。でもたったひとつだけ、どうしても欲しい星があった。それがお前だ」
「……」
涙が零れた。
唐突に、わかったのだ。
私は愛されている。
今までも、たぶん、愛されていたのだと。
「俺はお前が好きだ。ダリヤ、お前は、俺が好きか?」
顎の下で交差するバスィーム王子の腕に指をかけて、私は答えた。
「はい」
星空の下で交わされたキスを、私は一生忘れないだろう。
私をかけがえのない存在だと教えてくれた、愛しい人の眼差しも。