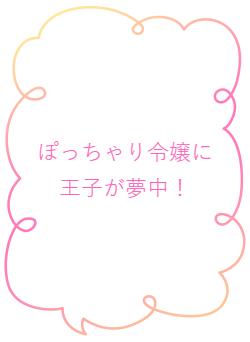「き、気持ちって……」
「ダリヤ」
バスィーム王子が近づいてくる。
いつもと違う、笑いの欠片もない真剣な表情が月に照らされている。
私は唇を舐めて、妙に荒くなった息を鼻息で逃がした。
「お前が好きだ、ダリヤ」
「……」
「お前は? 俺を好きか?」
直球だ。
目が燃えるように熱い。頬が熱い。首も熱い。ぜんぶ熱い。
「その……っ、私は、こういうのは慣れていなくて」
「わかっている」
「なので、あの……昼間のアレが、私は……」
「嫌だった?」
「嫌じゃ、なかったですけど……っ」
「けど?」
「その、確信がないんです」
「ほう」
王子の手が私の頬にのびる。
「ダリヤ」
バスィーム王子が近づいてくる。
いつもと違う、笑いの欠片もない真剣な表情が月に照らされている。
私は唇を舐めて、妙に荒くなった息を鼻息で逃がした。
「お前が好きだ、ダリヤ」
「……」
「お前は? 俺を好きか?」
直球だ。
目が燃えるように熱い。頬が熱い。首も熱い。ぜんぶ熱い。
「その……っ、私は、こういうのは慣れていなくて」
「わかっている」
「なので、あの……昼間のアレが、私は……」
「嫌だった?」
「嫌じゃ、なかったですけど……っ」
「けど?」
「その、確信がないんです」
「ほう」
王子の手が私の頬にのびる。