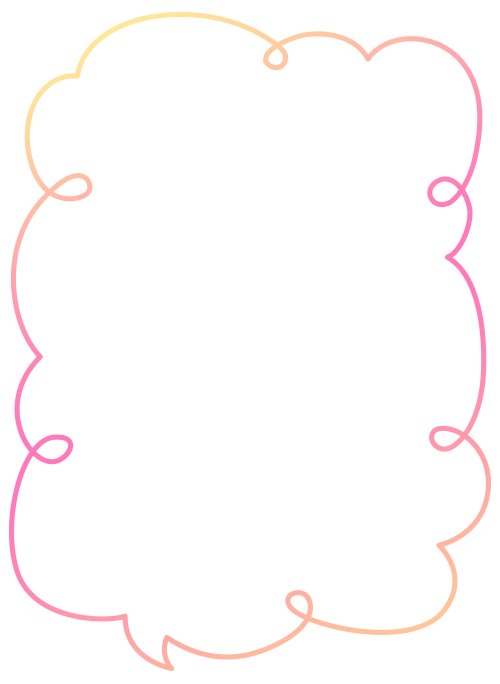「……っ!!」
「……あっ」
彩乃が息をのんだのと、岬が声を発してしまったのは同時だった。吸い寄せられるように彩乃の頬の触れてしまっていた。さっと手を引く岬を、潤んだ目の彩乃が見る。
「ごっ、ごめんっ!」
岬は素早く立ち上がり、走り出す勢いで彩乃の部屋を辞した。普段なら走らない廊下をダッシュで自分の部屋に戻る。バタンと後ろ手にドアを閉める岬に、マルたち親子が寄って来た。
「……なんで……、……そんな、いまさら……」
寄ってくるのか。
にゃーんと鳴いたマルたち親子はふさふさの尻尾で岬の足を代わる代わる撫でた。四匹を腕にぎゅうっと抱き締めてしまって、胸の動悸を抑え込む。
にゃん。
マルたちの不平も、今は聞かない。
「お前たちなんか……、ずっと彩乃にべったりだったくせに……」
なんだってこんな時に、岬を慰めるみたいに……。
なんだってこんな風に、慰められなきゃいけないんだ……。
脳裏に思い浮かぶのは泣きそうな顔の彩乃。そんな顔をさせたのは誰なのか。生徒会長やバレー部のエースアタッカー、バスケ部の部長や野球部のピッチャー。思い浮かぶ人の顔は沢山あるけど。
「お前なんか……、お前なんか……」
嫌いだった、はずなのに……。
猫たちの体に顔を埋める。
(お前なんか……)
絶対好きにならない。
そう思った方が負けなんだって、もうどこかで知っていた――――。