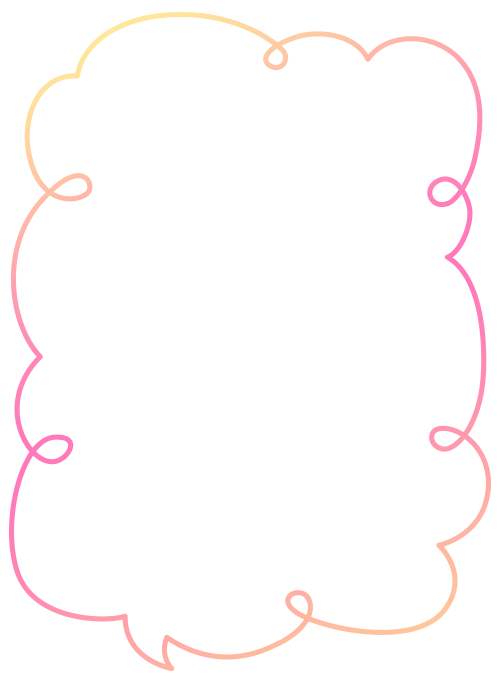「君の姿を見るまで、すごくすごく不安だった。情緒不安定でごめんね。こんな王子、嫌だよね? でも、今だけ。少しだけだから……」
私の肩に顔を埋めてきた。濡れた肩が温かい。
啜り泣く間に「良かった、良かった……」と彼は何度も呟いていた。子供のように縋ってくるエドの背中に、そっと手を回す。なんて声を掛けたらいいのかわからない。『恋の病』なんて話を鵜呑みにしたなら、こんなに泣かないような気がするのだけど……。
いつも遠慮のない愛をぶつけてくるエドワード王子が、何を考えているのか。何を思っているのか。私が知るのは、ただ彼が『リイナ=キャンベル』をとても愛しているということだけ。
私は本当の『リイナ』じゃない。彼の愛した『リイナ』とは別人格の人間。ただ『リイナ』の姿をした別の人。
そんな私に、本当は彼に心配してもらう権利も、想ってもらう権利もないのだから。
かけていい言葉なんて、何も思いつかなくて。
「よし、もう終わり!」
そう顔をあげると、エドはニコリといつもの優しい笑みを見せてくれる。
「ねぇ、リイナ。最後に一つだけ聞いていいかな?」
「……なんですか?」
「僕は君の理想の王子様になれたかな?」
そんな『私』の理想になろうと、頑張ってくれる王子様。
何も知らず、頑張ってくれる王子様。
もしかしたら、そんなあなたを滑稽だと笑う人もいるのかもしれない。
でも、私の中にはただただ嬉しいと、慈しみたくなる気持ちでいっぱいになる。
あなたから本当に愛されたいと、そう願う私でいっぱいになる。
「はい、今日のエドはとっても素敵でした」
私が頷くと、エドは嬉しそうにはにかんだ。
「良かった――今日は本当に来てくれてありがとう。僕も遅くなっちゃいそうだし、リイナはもう帰っていいからね。いつもの所に馬車を手配しておくね。宰相にも言っておくから大丈夫だよ」
「え、でも……」
正直あまり長居した場所ではないけれど、
「他の人に見せたくないって言ったでしょ? それとも、本当に閉じ込められたいの?」
ムッと拗ねた顔を見るや、絶対にそこを譲るつもりがないようで。私が肩を落とすと、彼は「ふふ」と笑って踵を返した。
「それじゃあ、また明日」
また明日――そう言うってことは、きっと明日の朝も迎えに来るのだろう。ダンスパーテイは今日で一段落だ。またお散歩やジョギングの日々が始まるのだろうか。
あの愛を叫び合うのだけは勘弁してほしいなぁと苦笑しながらも、私は「また明日」と言葉を返す。
たとえ、泥沼のような気持ちに足を踏み入れてしまうのだとしても。
彼が扉を締める直前、私とエドはお互い顔を見て笑い合った。そのささやかな約束が嬉しかったからだ。
私の肩に顔を埋めてきた。濡れた肩が温かい。
啜り泣く間に「良かった、良かった……」と彼は何度も呟いていた。子供のように縋ってくるエドの背中に、そっと手を回す。なんて声を掛けたらいいのかわからない。『恋の病』なんて話を鵜呑みにしたなら、こんなに泣かないような気がするのだけど……。
いつも遠慮のない愛をぶつけてくるエドワード王子が、何を考えているのか。何を思っているのか。私が知るのは、ただ彼が『リイナ=キャンベル』をとても愛しているということだけ。
私は本当の『リイナ』じゃない。彼の愛した『リイナ』とは別人格の人間。ただ『リイナ』の姿をした別の人。
そんな私に、本当は彼に心配してもらう権利も、想ってもらう権利もないのだから。
かけていい言葉なんて、何も思いつかなくて。
「よし、もう終わり!」
そう顔をあげると、エドはニコリといつもの優しい笑みを見せてくれる。
「ねぇ、リイナ。最後に一つだけ聞いていいかな?」
「……なんですか?」
「僕は君の理想の王子様になれたかな?」
そんな『私』の理想になろうと、頑張ってくれる王子様。
何も知らず、頑張ってくれる王子様。
もしかしたら、そんなあなたを滑稽だと笑う人もいるのかもしれない。
でも、私の中にはただただ嬉しいと、慈しみたくなる気持ちでいっぱいになる。
あなたから本当に愛されたいと、そう願う私でいっぱいになる。
「はい、今日のエドはとっても素敵でした」
私が頷くと、エドは嬉しそうにはにかんだ。
「良かった――今日は本当に来てくれてありがとう。僕も遅くなっちゃいそうだし、リイナはもう帰っていいからね。いつもの所に馬車を手配しておくね。宰相にも言っておくから大丈夫だよ」
「え、でも……」
正直あまり長居した場所ではないけれど、
「他の人に見せたくないって言ったでしょ? それとも、本当に閉じ込められたいの?」
ムッと拗ねた顔を見るや、絶対にそこを譲るつもりがないようで。私が肩を落とすと、彼は「ふふ」と笑って踵を返した。
「それじゃあ、また明日」
また明日――そう言うってことは、きっと明日の朝も迎えに来るのだろう。ダンスパーテイは今日で一段落だ。またお散歩やジョギングの日々が始まるのだろうか。
あの愛を叫び合うのだけは勘弁してほしいなぁと苦笑しながらも、私は「また明日」と言葉を返す。
たとえ、泥沼のような気持ちに足を踏み入れてしまうのだとしても。
彼が扉を締める直前、私とエドはお互い顔を見て笑い合った。そのささやかな約束が嬉しかったからだ。