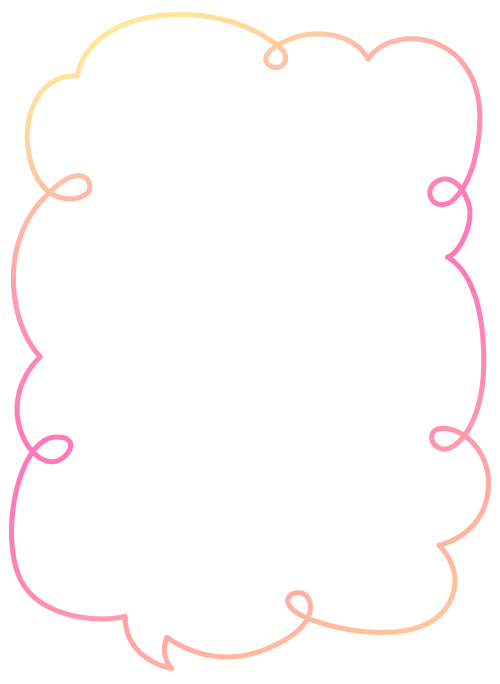「伊達にいつも芋を剥いていると思うなよ。まぁ、芋に粘り気があるからか思ったような軽さが出てないし、青のりも香草の粉末で代用してみたからまんまとは言えないが、これから試行錯誤を重ねて……て、聞いてるか?」
もうそれどころはない。よだれをズズッと啜ってしまうが、今日だけは許してほしい。
だって、ポテチなのだ。
前世で腹いっぱい死ぬほど食べてみたいと思っていた神の食べ物を、まさか中世ヨーロッパ風の異世界で食べれるなんて、夢にも思わないじゃない?
あぁ、神様ありがとう。私今まで、生きててよかった。
「あぁ……もうそんな目をキラキラさせて。やるから。そんな餌を目の前にした犬みたいにハァハァしなくてもやるから!」
押し付けられた羽のような小判に、私は生唾を呑み込んでから歯を立てる。
――サクッ。
シンプルなその音と口腔内に広がる香ばしい塩っけに、私の涙腺は自然と緩んだ。
「美味しい……美味しいよぉ……」
「ははっ、そりゃあ良かったな」
まるで他人事のように言うショウも一枚食すも、「まだまだだな」と首を傾げている。てやんでぃ。神の小判を侮辱するとは何たる無礼か。
「不満ならいいです。私が全部食べてあげます」
「いやいやいや、また他のも作ってやるから。少しにしておけって! 王子にダイエットさせておいて、きみが肥えたら示しが付かないだろう?」
「やぁーだぁー! 食べるのー?」
近くの木に止まった小鳥が今日もチュンチュン鳴いている。あぁ、今日も健康で良かったなぁ。ショウから奪うことが出来れば、夢にまで見たポテチが食べ放題だ!
「待て、待てって! そうだ! 今度はお好み焼きなんてどうだ? 和風味になるからチヂミっぽくなるかもしれないが……」
「お好み焼き? た、たこ焼きは?」
「たこ焼きはまず、あの鉄板がなぁ……」
そんなやり取りをしていると、どこからか「ショオオオオオオオオオゥ」という野太い声があがる。それに私が思わずポテチを落とすと、呼ばれた張本人が「悪い」と気のない謝罪をした。
「なんか料理長が怒っているらしい。何かな、油の後始末でも忘れてたかな」
「すごーく怒っているっぽいけど、大丈夫なの?」
「大丈夫大丈夫。たまにゲンコツ食らうのも悪くないもんだぜ」
私が尋ねると、ショウはなぜか嬉しそうで。そして全くこの場を片付ける様子もなく聞いてくる。
「そういや、きみは何か特殊能力はないのかい?」
「ない」
「え?」
「何にもない」
「……貴族だから魔法とかは?」
「全く使えなかった」
「そうか……まぁ、ポテチいっぱい食べなよ」
「……うん」
今日もランデール王国は、とても良い天気だ。
もうそれどころはない。よだれをズズッと啜ってしまうが、今日だけは許してほしい。
だって、ポテチなのだ。
前世で腹いっぱい死ぬほど食べてみたいと思っていた神の食べ物を、まさか中世ヨーロッパ風の異世界で食べれるなんて、夢にも思わないじゃない?
あぁ、神様ありがとう。私今まで、生きててよかった。
「あぁ……もうそんな目をキラキラさせて。やるから。そんな餌を目の前にした犬みたいにハァハァしなくてもやるから!」
押し付けられた羽のような小判に、私は生唾を呑み込んでから歯を立てる。
――サクッ。
シンプルなその音と口腔内に広がる香ばしい塩っけに、私の涙腺は自然と緩んだ。
「美味しい……美味しいよぉ……」
「ははっ、そりゃあ良かったな」
まるで他人事のように言うショウも一枚食すも、「まだまだだな」と首を傾げている。てやんでぃ。神の小判を侮辱するとは何たる無礼か。
「不満ならいいです。私が全部食べてあげます」
「いやいやいや、また他のも作ってやるから。少しにしておけって! 王子にダイエットさせておいて、きみが肥えたら示しが付かないだろう?」
「やぁーだぁー! 食べるのー?」
近くの木に止まった小鳥が今日もチュンチュン鳴いている。あぁ、今日も健康で良かったなぁ。ショウから奪うことが出来れば、夢にまで見たポテチが食べ放題だ!
「待て、待てって! そうだ! 今度はお好み焼きなんてどうだ? 和風味になるからチヂミっぽくなるかもしれないが……」
「お好み焼き? た、たこ焼きは?」
「たこ焼きはまず、あの鉄板がなぁ……」
そんなやり取りをしていると、どこからか「ショオオオオオオオオオゥ」という野太い声があがる。それに私が思わずポテチを落とすと、呼ばれた張本人が「悪い」と気のない謝罪をした。
「なんか料理長が怒っているらしい。何かな、油の後始末でも忘れてたかな」
「すごーく怒っているっぽいけど、大丈夫なの?」
「大丈夫大丈夫。たまにゲンコツ食らうのも悪くないもんだぜ」
私が尋ねると、ショウはなぜか嬉しそうで。そして全くこの場を片付ける様子もなく聞いてくる。
「そういや、きみは何か特殊能力はないのかい?」
「ない」
「え?」
「何にもない」
「……貴族だから魔法とかは?」
「全く使えなかった」
「そうか……まぁ、ポテチいっぱい食べなよ」
「……うん」
今日もランデール王国は、とても良い天気だ。