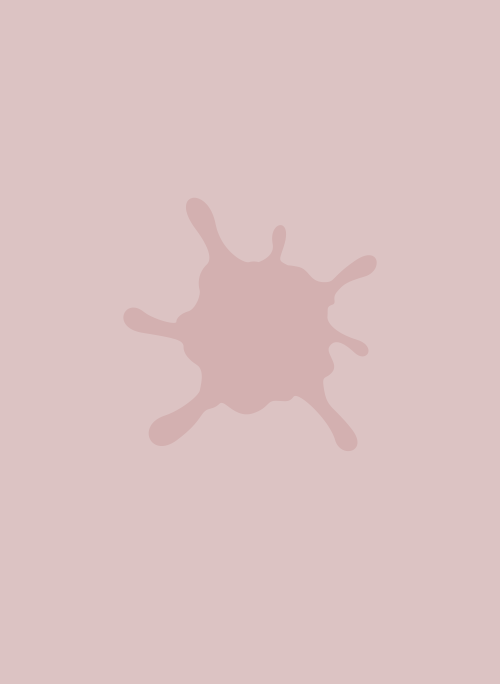あたしも殺されるんじゃないだろうか?
そう思うと全身から血の気が引いていった。
「これつけて」
いつの間に準備していたのか、お母さんがあたしに絆創膏を渡してきた。
手鏡で確認しながら数字の上に貼り、周りの髪の毛で絆創膏を隠す。
一見すればわからなくて、ひとまずホッとため息を吐き出した。
この数字が見えなければ攻撃されることはない。
しかし、安心したのもつかの間だった。
街から出る寸前でビーッビーッという警告音が聞こえ始めたのだ。
大きな音にとっさにお父さんは路肩に車を停止させた。
「なんの音だ!?」
「わからないわ!」
大声を出さないと互いの声も聞こえないほどの音。
その音はまるで自分の体の中から聞こえてきている気がして、あたしは座った状態でうずくまった。
「なに? どうなってるの?」
そんな自分の声はかき消されてしまう。
「来た道を少し戻ってみるか」
なにかに感づいたお父さんがそういい、車をUターンさせた。
そして少し走らせると、警告音はピタリと止まったのだ。
そう思うと全身から血の気が引いていった。
「これつけて」
いつの間に準備していたのか、お母さんがあたしに絆創膏を渡してきた。
手鏡で確認しながら数字の上に貼り、周りの髪の毛で絆創膏を隠す。
一見すればわからなくて、ひとまずホッとため息を吐き出した。
この数字が見えなければ攻撃されることはない。
しかし、安心したのもつかの間だった。
街から出る寸前でビーッビーッという警告音が聞こえ始めたのだ。
大きな音にとっさにお父さんは路肩に車を停止させた。
「なんの音だ!?」
「わからないわ!」
大声を出さないと互いの声も聞こえないほどの音。
その音はまるで自分の体の中から聞こえてきている気がして、あたしは座った状態でうずくまった。
「なに? どうなってるの?」
そんな自分の声はかき消されてしまう。
「来た道を少し戻ってみるか」
なにかに感づいたお父さんがそういい、車をUターンさせた。
そして少し走らせると、警告音はピタリと止まったのだ。