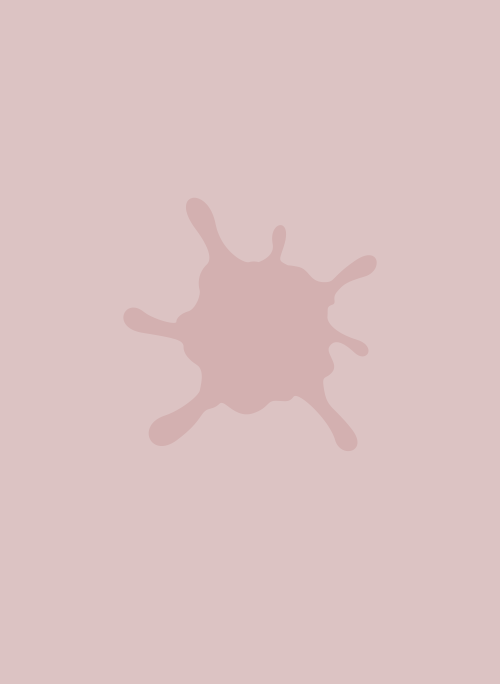「確かに君は真面目かもしれない。でも、大人からすればその他大勢の生徒と同じようなものだ」
「そんな……」
「現に、普段の生活態度なんて無視して商品に選ばれただろう? そんなもんなんだよ」
「納得できません!」
こういう言い方は悪いかもしれないけれど、商品としてふさわしい生徒は他にいると思っている。
「君たちから見ても、大人は全員同じじゃないのか」
「え……」
聞かれて、返事に詰まってしまった。
自分にとって特別な大人は両親だ。
先生も特別だと感じることはあるけれど、他の大人と変わらないと言われればそうかもしれない。
少なくとも、両親と先生と大人。
という大雑把なカテゴリーでしか別けていなかったのは事実だ。
「それと同じだ」
あたしはまた下唇をかみ締めた。
先生たちにとってはあたしはただのいち生徒。
そんなの言われなくてもわかっていたはずだ。
「……わかりました」
あたしは短く言い、木工教室を出たのだった。
「そんな……」
「現に、普段の生活態度なんて無視して商品に選ばれただろう? そんなもんなんだよ」
「納得できません!」
こういう言い方は悪いかもしれないけれど、商品としてふさわしい生徒は他にいると思っている。
「君たちから見ても、大人は全員同じじゃないのか」
「え……」
聞かれて、返事に詰まってしまった。
自分にとって特別な大人は両親だ。
先生も特別だと感じることはあるけれど、他の大人と変わらないと言われればそうかもしれない。
少なくとも、両親と先生と大人。
という大雑把なカテゴリーでしか別けていなかったのは事実だ。
「それと同じだ」
あたしはまた下唇をかみ締めた。
先生たちにとってはあたしはただのいち生徒。
そんなの言われなくてもわかっていたはずだ。
「……わかりました」
あたしは短く言い、木工教室を出たのだった。