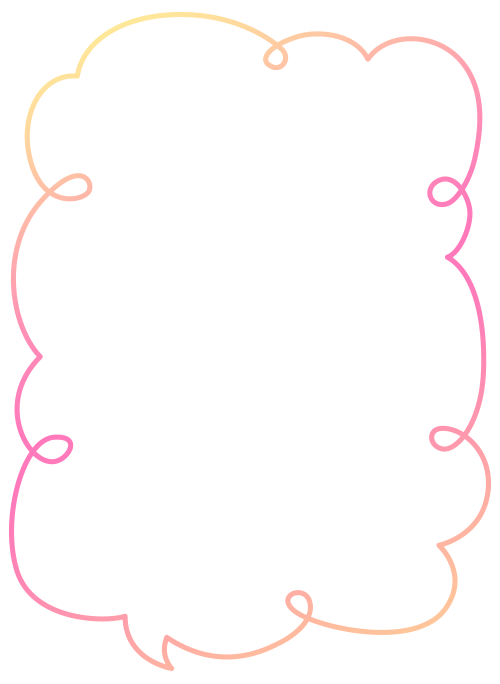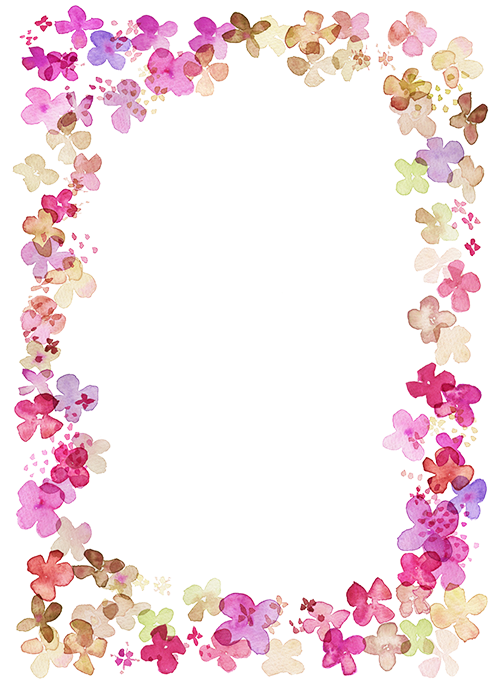そして、あの入試の日ペンケースを開けて絶句したのだ。
入れたはずの消しゴムが入っていなかったから。
母の仕業だと分かった。母はどうしてそこまであたしの足を引っ張るんだろう。
確かに高校に入学すればお金はかかるだろう。
だけど、そこまでしなくても。16歳になったらすぐにバイトをするって話もしたのに。
それなのに、どうして――。
あの時、涙が零れそうになって顔を持ち上げると、トンっと机の上に消しゴムが置かれた。
隣の席の女の子が消しゴムを貸してくれたのだ。
『よかったらこれ使ってください』
あたしのことなんて知らないはずの彼女の優しさに胸が温かくなって酷く動揺していた気持ちが落ち着いた。
『ありがとう……』
彼女は前を向いたまま頷いた。
あの時、萌奈があたしに消しゴムを差し出してくれなかったら今のあたしはここにはいないだろう。
高校に入学することも叶わなかっただろう。
彼女はあたしの恩人だ。
だから、今度はあたしがあの時の恩返しをする番だ。
入れたはずの消しゴムが入っていなかったから。
母の仕業だと分かった。母はどうしてそこまであたしの足を引っ張るんだろう。
確かに高校に入学すればお金はかかるだろう。
だけど、そこまでしなくても。16歳になったらすぐにバイトをするって話もしたのに。
それなのに、どうして――。
あの時、涙が零れそうになって顔を持ち上げると、トンっと机の上に消しゴムが置かれた。
隣の席の女の子が消しゴムを貸してくれたのだ。
『よかったらこれ使ってください』
あたしのことなんて知らないはずの彼女の優しさに胸が温かくなって酷く動揺していた気持ちが落ち着いた。
『ありがとう……』
彼女は前を向いたまま頷いた。
あの時、萌奈があたしに消しゴムを差し出してくれなかったら今のあたしはここにはいないだろう。
高校に入学することも叶わなかっただろう。
彼女はあたしの恩人だ。
だから、今度はあたしがあの時の恩返しをする番だ。