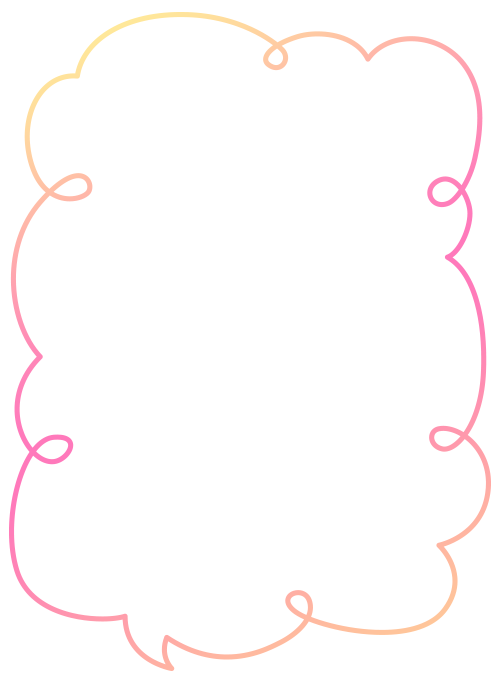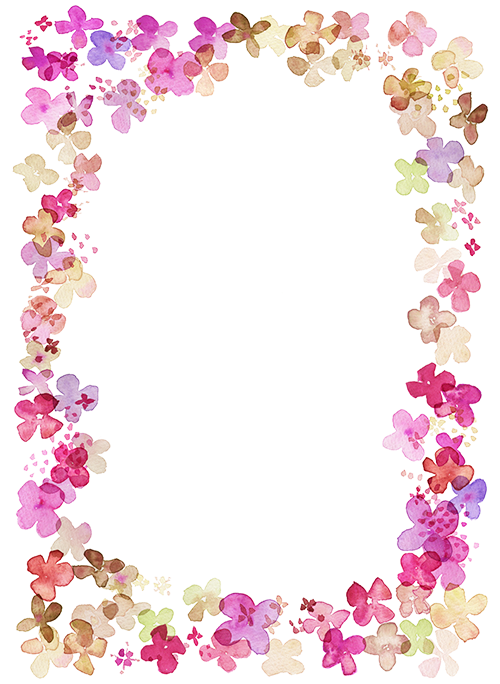「――さい」
暗闇の中、彼女は背中を丸めていた。
でもなぜかその背中が小刻みに震えている気がする。
「ごめんなさい」
彼女はかすれた声で電話口の相手に何度も何度も謝っている。
太陽のように明るくて眩しい彼女と、背中を丸めて今にも泣きだしてしまいそうなほど弱々しい声で謝っている彼女はまるで別人のようだった。
もしかしたら、リリカちゃんではないのかもしれない。
きっとそうだ。きっと別人だ。
足に根が張ってしまったかのように一歩も前で出すことができない。
駆け寄ることも、声を出すこともできずその場で立ち尽くしている間に、彼女は再び歩き始めた。
「違うよね……?」
どんどん小さくなっていく制服の少女がリリカちゃんではないことを私は願わずにはいられなかった。
暗闇の中、彼女は背中を丸めていた。
でもなぜかその背中が小刻みに震えている気がする。
「ごめんなさい」
彼女はかすれた声で電話口の相手に何度も何度も謝っている。
太陽のように明るくて眩しい彼女と、背中を丸めて今にも泣きだしてしまいそうなほど弱々しい声で謝っている彼女はまるで別人のようだった。
もしかしたら、リリカちゃんではないのかもしれない。
きっとそうだ。きっと別人だ。
足に根が張ってしまったかのように一歩も前で出すことができない。
駆け寄ることも、声を出すこともできずその場で立ち尽くしている間に、彼女は再び歩き始めた。
「違うよね……?」
どんどん小さくなっていく制服の少女がリリカちゃんではないことを私は願わずにはいられなかった。