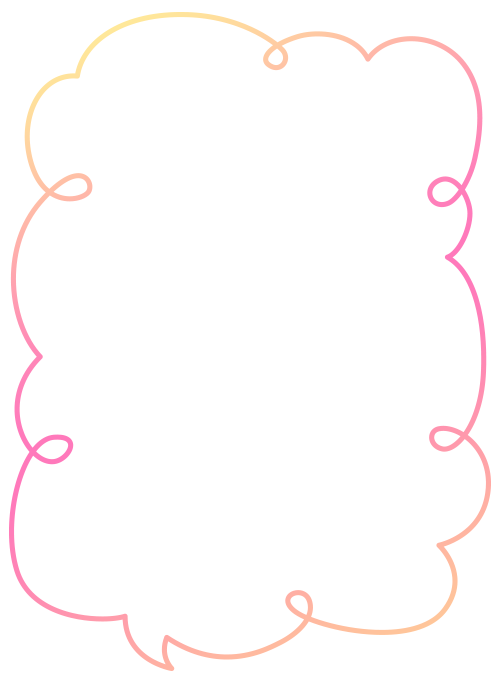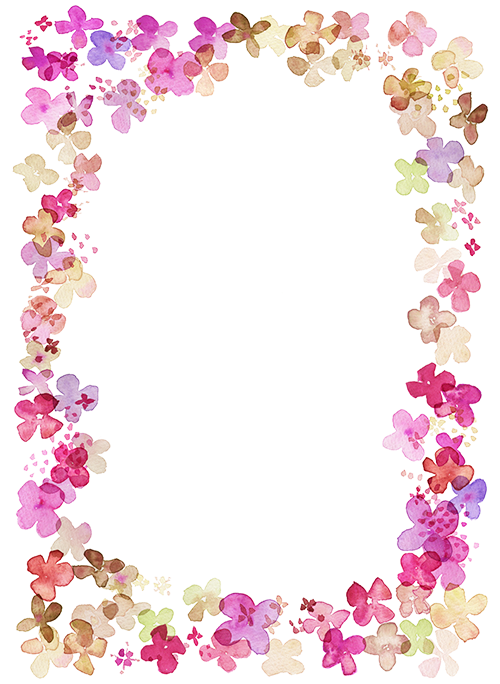私がどうしようもない人間だって思ってどんどん自己嫌悪に陥って、自己肯定感なんてほぼゼロになった。
劣等感ばかりが募って押しつぶされそうになり、ギリギリになってなんとか保っていたものがあの夏祭りの日にぽきっと折れてしまったんだ。
「苦しかったのに……辛かったのに……それを言えなかった。お母さんたちに話せば、きっと悲しむって思ったから。イジメられてるのを……知られなくなかったし、知られるのが怖かった」
「萌奈……」
母は黙って頷きながら目に浮かぶ涙を指で拭った。
「リリカちゃんに今日言われたの。あたしが萌奈のお母さんだったら、自分の娘が死のうとしたことにショックを受けるより、自殺しようと思うほど追い込まれてた娘の気持ちに気付いてあげられなかった自分を責める気持ちの方が大きいと思うよって。ごめんね、お母さん。私、自分のことばっかりでお父さんとお母さんの気持ち……考えられてなかった」
「そんなことないわ。私たちは萌奈が生きていてくれるだけでいい。それだけで。ただそれだけいいの」
「お母さん……」
涙が溢れる。今日の私は泣いてばかりだ。だけど、悲しい涙じゃない。
これは決意の涙。私はちゃんと前を向いて生きていく。リリカちゃんの言葉はまるで魔法のように私の心のポッカリとあいた隙間にはまった。
うまいことは言えないけどって言っていたけど、リリカちゃんは私の欲しい言葉を全部くれた。優しさで包み込んでくれた。
「リリカちゃんが言ってくれたの。萌奈の人生は萌奈だけのものだよって。それ聞いたら心の中のモヤモヤがスーって晴れた気がした。私は私のままでいいんだよって言ってもらってるみたいだった」
「そう。いいお友達ができてよかったわね」
「……うん」
ぽろぽろと涙を流しながら私と母は目を見合わせて笑った。
「そうだ。昨日リリカちゃんが買ってきてくれたスイーツ食べたら?」
「そうしようかな」
母が涙を拭ってパタパタとスリッパを鳴らしてキッチンへ駆けていく。
私は立ち上がり、部屋のカーテンを開けると夜空に輝く星を見上げた。
リリカちゃん、もう家に着いたかな。
私は夜空を見上げながらリリカちゃんへ思いをはせていた。
劣等感ばかりが募って押しつぶされそうになり、ギリギリになってなんとか保っていたものがあの夏祭りの日にぽきっと折れてしまったんだ。
「苦しかったのに……辛かったのに……それを言えなかった。お母さんたちに話せば、きっと悲しむって思ったから。イジメられてるのを……知られなくなかったし、知られるのが怖かった」
「萌奈……」
母は黙って頷きながら目に浮かぶ涙を指で拭った。
「リリカちゃんに今日言われたの。あたしが萌奈のお母さんだったら、自分の娘が死のうとしたことにショックを受けるより、自殺しようと思うほど追い込まれてた娘の気持ちに気付いてあげられなかった自分を責める気持ちの方が大きいと思うよって。ごめんね、お母さん。私、自分のことばっかりでお父さんとお母さんの気持ち……考えられてなかった」
「そんなことないわ。私たちは萌奈が生きていてくれるだけでいい。それだけで。ただそれだけいいの」
「お母さん……」
涙が溢れる。今日の私は泣いてばかりだ。だけど、悲しい涙じゃない。
これは決意の涙。私はちゃんと前を向いて生きていく。リリカちゃんの言葉はまるで魔法のように私の心のポッカリとあいた隙間にはまった。
うまいことは言えないけどって言っていたけど、リリカちゃんは私の欲しい言葉を全部くれた。優しさで包み込んでくれた。
「リリカちゃんが言ってくれたの。萌奈の人生は萌奈だけのものだよって。それ聞いたら心の中のモヤモヤがスーって晴れた気がした。私は私のままでいいんだよって言ってもらってるみたいだった」
「そう。いいお友達ができてよかったわね」
「……うん」
ぽろぽろと涙を流しながら私と母は目を見合わせて笑った。
「そうだ。昨日リリカちゃんが買ってきてくれたスイーツ食べたら?」
「そうしようかな」
母が涙を拭ってパタパタとスリッパを鳴らしてキッチンへ駆けていく。
私は立ち上がり、部屋のカーテンを開けると夜空に輝く星を見上げた。
リリカちゃん、もう家に着いたかな。
私は夜空を見上げながらリリカちゃんへ思いをはせていた。