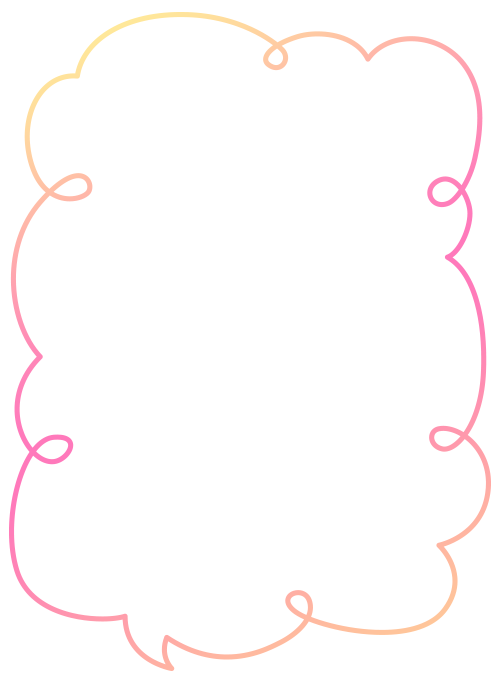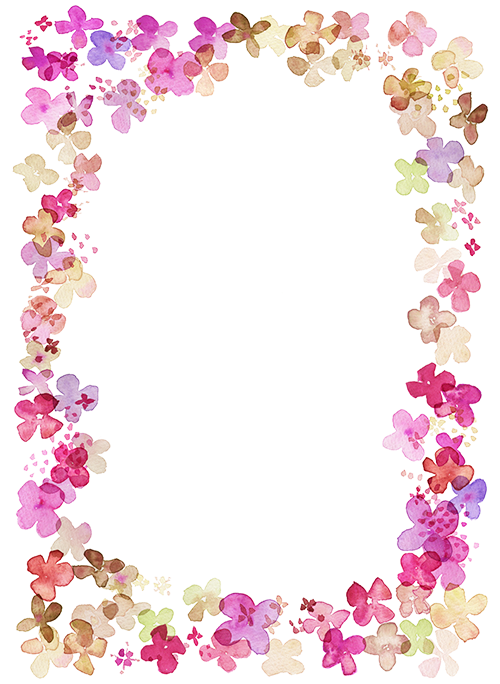「あたしはイジメられたことがないから、萌奈の苦しみも痛みも100%すべてを分かってあげることはできない。うまい言葉で励ましたりとかこうしたらいいんじゃない?みたいなアドバイスも得意じゃないよ。なんていったらいいかわかんない。だけどさ、こうやって一緒にいることはできるよ」
萌奈の体からそっと腕をほどき、Yシャツの袖で萌奈の涙をごしごしと拭う。
「リリカちゃん……」
「そばにいて話を聞くことはできるよ。なんか辛かったら電話してくれれば飛んでくし、愚痴りたくなったらラインちょうだいよ。あたし、何時まででも付き合うよ。あたしができることならなんだってするよ」
「それなら……」
「うん?」
「私もリリカちゃんのそういう存在になりたい」
「え?」
首を傾げると、萌奈は手の甲で涙を拭った。
目の縁を真っ赤に染めて、鼻をすすりながらぐちゃぐちゃの顔をあたしに向ける。
ひっくとしゃくりあげながらも萌奈はあたしをまっすぐ見つめた。
「ずっと思ってた。誰かに必要とされたいって。誰かの特別になりたいって。リリカちゃんは私にとって特別な人なの。だから、私もリリカちゃんの特別になりたい。必要とされたい」
「萌奈……」
「私……この世界に生きていていいんだって……今、思えたの。リリカちゃんのおかげで。リリカちゃんがそう思わせてくれた」
「えっ。嘘。マジで?あたし、すごくない?」
「ふふっ……なにそれ」
萌奈がふわりと笑う。やっぱり萌奈は笑っていた方が可愛い。
萌奈の体からそっと腕をほどき、Yシャツの袖で萌奈の涙をごしごしと拭う。
「リリカちゃん……」
「そばにいて話を聞くことはできるよ。なんか辛かったら電話してくれれば飛んでくし、愚痴りたくなったらラインちょうだいよ。あたし、何時まででも付き合うよ。あたしができることならなんだってするよ」
「それなら……」
「うん?」
「私もリリカちゃんのそういう存在になりたい」
「え?」
首を傾げると、萌奈は手の甲で涙を拭った。
目の縁を真っ赤に染めて、鼻をすすりながらぐちゃぐちゃの顔をあたしに向ける。
ひっくとしゃくりあげながらも萌奈はあたしをまっすぐ見つめた。
「ずっと思ってた。誰かに必要とされたいって。誰かの特別になりたいって。リリカちゃんは私にとって特別な人なの。だから、私もリリカちゃんの特別になりたい。必要とされたい」
「萌奈……」
「私……この世界に生きていていいんだって……今、思えたの。リリカちゃんのおかげで。リリカちゃんがそう思わせてくれた」
「えっ。嘘。マジで?あたし、すごくない?」
「ふふっ……なにそれ」
萌奈がふわりと笑う。やっぱり萌奈は笑っていた方が可愛い。